- 〇はじめに
- 〇1.プレイングマネージャーとは何か──PM職が生まれてきた背景
- 〇2.PMが勘違いしやすい落とし穴──失敗上司にならないために
- 〇3.スポーツのPMとの違い──リーダーシップとヴィジョンを共有する
- 〇4.業務効率化の3原則──PMとしての自主性と部下との対話
- 〇5.優秀なPMの条件──ストレスに負けない仕事をするために
- 〇6.破綻するPMの共通点──意外な盲点とは?
- 〇7.なぜ海外にはPMが少ないのか?──日本の現状との比較
- 〇8.中小企業経営者が取るべき視点──スモールステップのマインドとは?
- 〇9.名ばかり管理職と法的リスク──「管理権限」とは?
- 〇10.部下育成の5つの視点──やる気とやりがいの両立
- 〇おわりに
〇はじめに
昨今何かと話題になっているプレイングマネージャー(PM)という言葉。良き上司の理想像とされたり、あるいは働きすぎとして注意喚起の対象となることもあります。プレイングマネージャーは、とくに日本の中小企業で多く見られますが、そもそもPM(管理職にありつつ、現場でも業務を務める存在)の役割とは何なのでしょうか?
例えば……
A「今度昇進することになったよ!」
B「そうか、おめでとう。とうとう君も現場を離れることになるわけだ?」
A「いや、現場と兼務なんだよ。いわゆるプレイングマネージャーというやつ」
B「なんだ、そうなのか? 大変だなあ。部下も育成するんだろ? 心身ともに壊れないように気をつけろよ?」
A「ありがとう。なんとかやってみるよ!」
……こんなふうに、プレイングマネージャーというのは、企業で働く人間にとってはある種のあこがれであると同時に、働きすぎのリスクに陥ってしまいかねない危険をはらんでいます。PMになれば、自然と部下たちを管理・管轄することになり、それは管理職にある自分の地位にのしかかってくることでもあります。そこで負けないためには、どんなスタンスで仕事に臨めば良いのでしょうか?
こちらの記事では、日本におけるプレイングマネージャーの現状や、この職種が生まれてきた背景や意味、職場での苦労や現場における改善策、部下の育成などについての具体例を提示していきます。さらに、海外での事例や日本の現状との比較、法令によってプレイングマネージャーはどのようにとらえられているのか、なども解説しています。
部下とのコミュニケーションはどうするのか、自分の時間はいかに管理するか、そういった身近な話題にも触れています。──PMという職種にある人限定ではなく、企業や組織で働くみなさんも、一人の人間として、従業員として、部下をまとめる、部下といっしょに働く、ということがどのようなことであり、どんな課題があるのかを探っていきましょう。
〇1.プレイングマネージャーとは何か──PM職が生まれてきた背景
プレイングマネージャー(PM)という言葉は、現場で実務を担う「プレイヤー」と、現場の組織を管理・統括する「マネージャー」という二つの役割を一人で兼ねる存在を指します。
近年ではよく耳にするようになった言葉ですが、実は1990年代のバブル崩壊の前後から注目されるようになった比較的新しい概念です。当時、日本の企業は不況への対応として組織のスリム化やスピード重視といった方向に経営の舵を切り、人件費削減と効率化の流れが強まっていきました。そこで「現場と管理の兼務ができる」機動力を活かす働き方が求められ、自然とプレイングマネージャーという役割が広がっていったのです。
特にスタートアップ企業や中小・零細企業のように、職務の境界がゆるやかで「人が少ないからみんなでカバーする」文化がある現場では、プレイングマネージャーが生まれやすい傾向にあります。上意下達の縦割り型組織というよりも、顔を合わせて話し合いながら進める「協働」が回る環境だからこそ、「管理者でありながら実務もこなす」人材が不可欠となるわけです。
たとえば製造業の小規模工場では、ライン管理を担いつつ自ら検品作業にも入る係長がいたり、営業の現場では顧客との交渉をまとめながらチーム全体の数字を管理する課長がいたりします。こうした姿はまさにプレイングマネージャーの典型と言えるでしょう。
しかし、そもそもプレイヤーとマネージャーは役割期待が異なります。
プレイヤーは成果を「自分の手」で直接作り出すのに対し、マネージャーは「他者を通じて」成果を生み出すのが仕事です。前者にはスキルや瞬発力が、後者には判断力や育成力が必要とされます。両者を同時に担うPMは、時間と注意の配分が常に難しく、バランスが崩れれば「どちらも中途半端」に陥る危険がつきまとっているのです。成功すれば組織に大きな推進力を与えますが、失敗すれば本人も疲弊し、部下も育たず、経営層にとっても視界不良の原因となってしまいます。
ここで重要なのは、プレイングマネージャーは正式な制度上の職位ではなく、あくまで「役割の重なり」であると理解することです。
つまり、肩書きに明記されていなくても、実際の業務内容がプレイヤーとマネージャーを兼ねていれば、その人はPMとして働いていることになります。だからこそ、組織として「何を担ってほしいのか」「どの配分で時間を使うのか」「どの範囲の権限を与えるのか」を明確に言語化し、経営とPM本人が合意しておくことが出発点となります。これが曖昧なままだと、責任だけが押し付けられ、やりがいを失い、最終的には離職や組織の停滞につながりかねません。
プレイングマネージャーという存在は、日本的な組織文化が生んだ一つの現実的な解決策であり、時代の要請でもあります。その背景や特徴を理解したうえでこそ、職務上の「落とし穴」や「成功の条件」を考えることができるのです。
〇2.PMが勘違いしやすい落とし穴──失敗上司にならないために
プレイングマネージャー(PM)が最初につまずきやすいのは、「やる気があるのに、なぜか部下が育たない」「気づけば自分ばかりが忙しい」という状況です。そこには典型的な「落とし穴」が三つあります。ここで少し整理してみましょう。
第一の落とし穴は「私がやった方が早い症候群」です。
部下に任せれば時間がかかるし、出来も心配。つい「ここは自分が片付けた方が効率的だ」と考えてしまいます。短期的にはその通りなのですが、長期的には大きな損失になりかねません。なぜなら、いつまでも部下に経験値がたまらず、結局チーム全体の出力が上がらないからです。「任せる」こと自体が投資であり、時間のかかるプロセスなのだと思う必要があります。
第二の落とし穴は「成果の物差しの混線」です。
プレイヤーとしては自分の売上や自分のミス率が気になりますし、マネージャーとしては部下の育成や再現可能な仕組みづくりが成果物になります。この二つを同列に追いかけると、どちらも中途半端になりがちです。結果的に「どちらも伸びない」というジレンマに陥ります。重要なのは、自分の評価基準を意識的に切り替えることです。「今日はプレイヤーとして」「今はマネージャーとして」と心の中でラベルを貼り直すだけでも、迷いは減っていきます。
第三の落とし穴は「即応万能」という錯覚です。
チャットや電話に即レスしてトラブルを処理できれば、周囲からは頼もしく見えます。しかし、これを常態化すると「火消し役」に終始してしまい、組織の構造課題には手をつけられません。部下からの依頼に反射的に応じるのではなく、まずは「これは今すぐ対応すべきか?」「再発防止の仕組み作りが先か?」と一呼吸置くことが必要です。
そして、ここで忘れてはならないのが「肩代わりは善意の仮面をかぶった害」になり得るということです。プレイングマネージャーが代わりにやってしまえば、確かにその場はスムーズですが、部下の学びや経験の機会を奪ってしまいます。マネージャーとしての本業は「仕事ができる人を増やすこと」であり、自分一人で業務や責任を背負うことではありません。
そのために必要なのが「やらない勇気」です。スケジュール表に「この時間は管理専念」「この時間は部下に任せる」と書き込むだけでも効果があります。こうしたタイムマネジメントに気を遣うことで、現場と管理の両立がしやすくなっていきます。プレイングマネージャーの仕事とは結局、「自分を律しながら他者を育てる」ことに尽きるのです。
〇3.スポーツのPMとの違い──リーダーシップとヴィジョンを共有する
プレイングマネージャーという言葉を耳にすると、スポーツの世界を思い浮かべる方もいるかもしれません。
実際、選手としてグラウンドやコートに立ちながら、同時に監督やコーチとしてチームをまとめ上げた人たちがいます。プロ野球の古田敦也さん、サッカーの釜本邦茂さん、バスケットボールの岡村憲司さんは、その代表的な存在でしょう。彼らはいずれも現役選手として一流の実力を発揮しつつ、戦術を考え、仲間を鼓舞し、試合の流れを読む指導者としても振る舞いました。
例えば、古田選手は捕手として試合に出ながら、データを活かした戦術でチームを勝利に導いたといわれます。釜本選手は得点源としてピッチに立つと同時に、周囲の選手たちに自らの経験を伝え、試合全体を俯瞰する役割も担いました。岡村選手もまた、選手としての動きに加えてチームを鼓舞し、状況判断で若手を導くリーダーシップを発揮しました。こうした「選手兼任監督」の姿は、まさにスポーツならではのPM像といえるでしょう。
もっとも、スポーツにおけるプレイングマネージャーとビジネスのプレイングマネージャーは全く同じではありません。スポーツにはシーズンという区切りがあり、勝敗というはっきりした指標があります。一方で企業活動は終わりのない連続体であり、成果は売上や品質、組織の成長など複数の要素が複雑に絡み合います。その意味で、スポーツのPMはあくまでも特別な場面で輝く役割であり、ビジネスのPMとは性質が異なるのです。
しかし両者には確かな共通点もあります。それはリーダーシップと情熱、そして周囲を巻き込む力です。スポーツの現場で選手たちが自らを犠牲にしてでもチームを勝利に導いたように、ビジネス界のPMもまた、自らの成果だけではなく、チーム全体の成長と成果に目を向けることが求められます。人を動かすのは肩書きではなく、信頼と説得力なのです。
古田敦也さんの言葉を借りれば、それは次のようにも表現できます(*1)。
「指導者で一番大切なのは説得力」
「人の想いを背負ってる方が非常に力になる」
「できるできないなんて考えない。やれる方法しか考えない」
「どのデータが生かせるのか、どう生かせば良いのか。そこを徹底して考えた……」
「ちゃんと傾向を把握して対策を打ち、準備段階で敵より一歩前に出る」
こうした言葉には、スポーツに限らず、ビジネス界のPMにも通じる普遍的なヒントが込められているのです。
(*1) https://meigen.keiziban-jp.com/furuta_a
〇4.業務効率化の3原則──PMとしての自主性と部下との対話
「効率化」と聞くと、どうしても掛け声やスローガンのように響いてしまうものです。けれども、実際に現場で役立つのは小さな工夫の積み重ねです。ここでは、プレイングマネージャーが日々の業務で意識したい3つの原則を取り上げてみましょう。
まずは「ムリ・ムダ・ムラをなくす」という考え方です。
これは日本の生産現場で古くから大切にされてきたキーワードですが、PMにとっても十分応用がききます。たとえば、自分が参加している会議や承認作業、日常的なチャット対応を一度棚卸ししてみると、「本当に自分でなければならない仕事」と「部下やリーダーに任せてもよい仕事」が見えてきます。プレイングマネージャーしかできない判断はしっかりと自分が担い、それ以外は安心して人に任せる。これだけでも日々の余計な負担はぐっと減ります。
次に「やめる・減らす・変える」という視点です。
習慣になっている定例ミーティングや報告の場を見直し、必要があれば隔週にしたり、アジェンダをあらかじめテンプレート化したりするだけでも時間の節約につながります。あるいは会議そのものを「短く終える」工夫をするのも一つの手です。「すべてをゼロにしなければならない」と構える必要はなく、負担を少し減らすだけでも、結果として大きな余裕を生み出します。
三つ目は「ECRS(イクルス)の四原則」です。
これは、Eliminate(排除)、Combine(統合)、Rearrange(入れ替え)、Simplify(簡素化)の頭文字をとったものです。たとえば、似たような報告書が複数あるなら一つにまとめてしまう(EliminateとCombine)。承認の順番を工夫して業務の滞りをなくす(Rearrange)。報告の様式をシンプルにし、誰が作っても同じように仕上がるようにする(Simplify)。こうした工夫は、プレイングマネージャー自身の作業を軽くするだけでなく、部下にとっても迷いを減らす効果があります。
こうした原則を形にしていくうえで、具体的な工夫も役立ちます。
たとえば、自分のスケジュール帳に「管理の時間」と「現場の時間」をあらかじめブロックとして確保しておけば、自然と時間の配分が意識できます。また、部下へのフィードバックは長々と語るより「状況・行動・影響」という3つの切り口(SBI法)でまとめると、お互いに理解しやすくなります。さらに、決まったことは可能な範囲で文書にして共有しておくと、後で「言った・言わない」の混乱が防げます。これは義務というより、時間に余裕があるときの安心の工夫、と考えるとよいでしょう。
効率化の本当の目的は、PMが「余裕を持って考える時間」を確保することにあります。仕組みで迷いを減らし、対話で納得をつくる。その繰り返しが、チーム全体の力を静かに引き出していくのです。
〇5.優秀なPMの条件──ストレスに負けない仕事をするために
では、優秀なプレイングマネージャーとして評価され、現場でも活躍できるためには、どのようにふるまえばよいのでしょうか。
まず欠かせないのは「現場感覚」です。
これは単に「肌で感じる」ことではありません。数字や報告書で示されたデータと、実際に現場で起こっていることの差を見抜き、その理由を説明できる力のことです。たとえば「不良率は改善しているのに、現場の士気が下がっている」といったズレを捉えられる人は、現場感覚に優れていると言えるでしょう。
次に必要なのは「俯瞰力」です。
これは、一つ一つの部門やチームが最適化を追求するあまり、全体のバランスが崩れてしまう瞬間を察知する力です。個々の成功が組織全体の失敗につながることは珍しくありません。優秀なプレイングマネージャーは、全体を見渡す鳥の目を持ち、どの調整が必要かを考えられます。
三つ目は「対話力」です。
これは単なるコミュニケーション上手というよりも、相手の自主性や自立性を引き出す問いを投げかけられる力です。評価を与えるときと、支援を行うときとを切り分け、相手が自分で考え、動けるように促します。問いかけ一つで、部下の動機づけや気づきは大きく変わっていきます。
加えて、優秀なプレイングマネージャーにとって有効な二つの力があります。それが「数値化」と「物語化」です。
「数値化」とは、成果を測るための共通言語をチーム内に持つことです。数字は客観的で、誰にでも共有しやすい指標になります。たとえば「今月の問い合わせ件数を20%減らす」といった具体的な目標を示せば、メンバーは何に取り組めばいいのかをよりはっきりと理解できます。
一方で「物語化」も同じくらい重要です。人は数字だけでは動きません。数字に込められた意味や背景を語り、物語として共有することで、メンバーは自分の仕事に納得感を持てます。「ここを改善すれば、お客様がもっと安心してサービスを利用できる」といったストーリーがあれば、チームは自然と力を発揮しやすくなるのです。
ここで気をつけたいのは、「万能さの罠」です。プレイングマネージャーは現場にも管理にも通じているため、「自分がやった方が早い」と考えてしまいがちです。しかし、自分ができることと、やるべきことは必ずしも一致しません。境界線を引き、部下に任せ、そして見届ける。そのサイクルを意識することが、優秀なプレイングマネージャーとして成長するための鍵となります。
ストレスに負けないとは、無理に我慢することではありません。抱え込まずに仕組みを作ること。その余白のなかに、PMとしての強さが育まれていくのです。
〇6.破綻するPMの共通点──意外な盲点とは?
どんなに優秀に見えるプレイングマネージャーでも、気づかぬうちに「破綻のパターン」に陥ってしまうことがあります。それは突然起こるものではなく、日々の積み重ねが少しずつ限界を超えていくような形で訪れます。ここでは代表的な例を挙げてみましょう。
まずよくあるのが「私がやった方が早い」という思い込みです。確かに短期的には早く片づきますが、大事な仕事をいつまでも任せなければ、部下の成長は止まり、結局PMだけが常に多忙になります。これは「委譲不全」と呼ばれる典型的な罠です。
次に「万能感と被害者意識の往復」です。「責任や厄介ごとは全部自分に来る」と不満を抱えながらも、「結局自分がやるしかない」と背負い込んでしまう。この繰り返しは心身をすり減らし、燃え尽きに直結します。
三つ目は「優先順位の無秩序」です。目の前に飛び込んでくる「緊急的な」依頼が常に意識の上で勝り、重要な課題が結局後回しになる。結果として、火消しばかりに追われて長期的な改善ができず、チーム全体の力も伸びなくなります。
最後に「孤立」があります。相談相手がいない、弱音を吐けないという状況は、プレイングマネージャーにとって特に危険です。孤立したPMは判断を一人で抱え込みやすく、無理を続けた末に突然倒れてしまうことさえあります。
これらのパターンに共通する盲点は、「善意が構造を悪化させる」ということです。誰かを助けたい気持ちや、自分がやった方が確実だという思い込みは、一見プラスに見えます。しかし実際には、部下の学習機会を奪い、問題の根を覆い隠し、プレイングマネージャー自身の稼働を圧迫していきます。
では、どうすれば破綻を防げるのでしょうか。ここでは三つの視点を簡単に示しておきましょう。
個人レベルでは、「NOリスト」を作ることが有効です。自分でなくてもよい依頼は思い切って断り、やるべき仕事に集中する勇気を持ちましょう。
チームレベルでは、役割と期待のマトリクスを共有することです。「誰がどの事案と結果に責任を持つのか」を明確にすることで、負担の偏りを防ぎ、部下の自律も育ちます。
組織レベルでは、プレイングマネージャー同士のピアレビューやメンタリング、定例の1on1といった仕組みを整えることが重要です。相談できる場はぜいたくではなく、組織のリスクを減らすための必須条件なのです。
プレイングマネージャーを孤立させることは、結局は組織全体の疲弊や損失につながります。だからこそ、一人で抱え込ませないための仕組みづくりこそが、最も費用対効果の高い投資なのです。
〇7.なぜ海外にはPMが少ないのか?──日本の現状との比較
「プレイングマネージャー」という言葉は日本ではよく耳にしますが、欧米企業ではあまり一般的ではありません。そこには企業風土や法制度の違いが大きく影響しています。
まず、その大きな理由は「ジョブディスクリプション(職務記述書)」の存在があるためです。
欧米では、職務の範囲・権限・責任がセットで明確に定義されており、管理職は評価や労務管理、資源配分といった仕事に専念します。一方、非管理職は労働時間の保護や職務範囲の明確さによって守られており、両者の線引きがとてもはっきりしています。そのため、「現場でプレイヤーをしながら管理職を兼ねる」という働き方は例外的な存在になりやすいのです。
次に、キャリア観の違いもあります。
欧米ではキャリアの進み方が「二方向」に分かれるのが一般的です。専門職の人はプレイヤーとしてスキルを磨き、市場価値を高めていく。一方で、マネジメント志向の人は「人や仕組みを動かす」方向に進む。この二つのルートは重なりにくく、規模が大きくなるほど役割は細分化されます。結果として、選手兼監督のようなPlayer-Coach型の立場は成立しにくくなります。
さらに、欧米では「専門家志向」が強いことも特徴です。現場で専門性を磨いた人はそのままスペシャリストとして評価され、現場にとどまり続けるようになります。そして、さらに上を目指す人は管理職として別のトラックに移行するのです。日本のように「なんでもこなせるジェネラリスト」が評価されるのとは対照的だと言って良いでしょう。
とはいえ、例外も存在します。スタートアップ企業やクリエイティブ業界のように、少人数でスピード感が重視される領域では、PM的な働き方をする人も少なくありません。
代表的なのが、ゲーム『マインクラフト』の開発者マルクス・ペルソン氏です。彼は作品の大成功によって会社を拡大しましたが、大企業の経営者として会社の方向性だけを決める立場に満足できず、最終的には役員を退きました。そして現在は小規模な組織を立ち上げ、再び開発現場に深く関わるスタイルを選んでいます。この例は、プレイングマネージャー的な立場にこそ創造性や充実感を見いだす人間がいることを示していて、とても興味深い挿話です。
一方、日本では文化的な背景もあり、プレイングマネージャーが広がりやすい土壌があります。
ジェネラリストが評価される傾向が強く、「現場もできるし、マネジメントもできる」ことがキャリアの武器になる。相互扶助的な組織文化もそれを後押ししています。強みは柔軟さと速度ですが、その反面として「属人化」(特定の地位にある人しか知識をもっていない)や「曖昧さ」(業務自体が惰性になる)がつきまといます。だからこそ、役割や権限の定義を補強しつつ、日本型の強みをどう活かしていくかが問われているのです。
〇8.中小企業経営者が取るべき視点──スモールステップのマインドとは?
中小企業においては、経営者自身がかつてプレイヤーやプレイングマネージャーとして働いていたという場合も多いでしょう。そのため「現場の苦労は自分も知っている」と思い込みがちです。しかし、組織全体を見渡す立場になった時に必要なのは、過度な効率化や縦割りの仕組みに頼ることではなく、PMを支える仕組みそのものを設けることです。PMが孤立してしまえば現場は弱り、経営の未来も見えにくくなります。
ここではPMを支える「三つの柱」を中心に考えてみましょう。
第一に、メンタリングです。
経営層が過去の経験や組織の方向性を伝えることは、単なる知恵の共有ではなく、プレイングマネージャーの意思決定を支える大切な後押しになります。たとえば「自分もかつてはこういう場面で悩んだ」という経験談を共有するだけでも、PMにとっては精神的な安心になります。単なる指示ではなく「ともに考える」という姿勢が、PMの自発的な成長を促すのです。
第二に、業務分散です。
プレイングマネージャーが抱え込む業務を棚卸しし、「自分でなければならないこと」と「部下に任せられること」を切り分けることも大事です。ここで重要なのは、単純に仕事の量を分散するのではなく「責任の所在」を明確にすることです。部下に任せた部分については、成果の責任も含めて委ねる。PMは「業務の妨げになることを取り除く」ことに集中する。そうすることで時間の配分に余裕が生まれ、管理と現場のバランスを取りやすくなります。
第三に、1on1を含めた対話の場です。
PM同士が横でつながる場や、現場から経営に声が届く仕組みを整えることは、現場の疲弊を防ぐ大きな力になります。縦の関係だけではなく、横や斜めの関係を意識的に設計することで、プレイングマネージャーは「相談できる相手がいる」という安心感を持ちやすくなります。これがあるだけで、孤独感や過度な責任感が和らぎ、前向きな判断がしやすくなるのです。
経営者に求められるのは「任せる」と「守る」の両立です。ただ任せるだけではプレイングマネージャーは消耗し、ただ守るだけでは育ちません。両方のベクトルを同時に持つことが、組織に長く息づく仕組みづくりにつながるのです。
補足として、小さな改革を積み重ねていく「スモールステップ」の発想も紹介しておきましょう。たとえば30日、60日、90日と段階を区切り、最初は「業務の棚卸」や「権限の可視化」といった基礎を固め、その後に小さな実験を重ねて定着を図る。大規模改革に比べて遠回りに見えますが、むしろ着実で効果の高い方法です。
プレイングマネージャーが本来の業務に集中できる環境を整えることは、現場に活力をもたらし、経営層にとっても企業の未来を描きやすくする最良の投資になります。
〇9.名ばかり管理職と法的リスク──「管理権限」とは?
プレイングマネージャーの役割を現場に寄せすぎてしまうと、「管理者であるはずなのに、実態はただの便利屋」という状態になりかねません。この場合、企業にとっては法的なリスクが発生します。名ばかりで管理職扱いを続けていると、従業員からの信頼を失うだけでなく、労働基準法違反として企業そのものが処罰対象になる可能性があるのです。
労働基準法上の「管理監督者」とは、単に役職名で判断されるものではありません。ポイントは三つあります。①経営者と一体的な立場にあること(人事や労務、予算に関わる実質的な権限を持つこと)、②労働時間に裁量があること(出退勤の自由度が高く、強く拘束されていないこと)、③その責任に見合った処遇を受けていること。……これらがそろっていなければ、たとえ「課長」「店長」といった肩書きを持っていても、法的には管理監督者と認められません。
この点をめぐって大きな話題となったのが、マクドナルドの「名ばかり店長」訴訟です。形式的には店長とされ、管理職手当も支給されていましたが、実際には人事や予算を取り扱う権限がなく、労働時間の自由度もないまま長時間労働を強いられていました。裁判所は「実態は一般従業員と同じ」と判断し、残業代の支払いを命じています。こうした判例は、企業が「肩書きだけの管理職」を置くことに大きな警鐘を鳴らしました。
違反が発覚した場合、未払い残業代の請求だけでなく、是正勧告や追徴、さらには6か月以下の懲役または30万円以下の罰金といった罰則が科される可能性があります。つまり「名ばかり管理職」は、経営にとっても現場にとってもリスク以外の何ものでもないのです。
では、どうすればよいのでしょうか。まず大切なのは、ジョブディスクリプションを用いて役割と権限を明文化することや、勤怠管理を適正に行うことです。「この範囲まではPMが判断できる」「この範囲は経営層に委ねる」「定時以降に現場で業務を依頼する場合は、事前に承認を得る」といったルールを設けると、プレイングマネージャーの立場は守られやすくなります。
さらに、処遇の見直しも重要です。責任に見合った管理職手当や評価制度を整えなければ、プレイングマネージャーのモチベーションは維持できません。権限と報酬が釣り合っていると実感できてこそ、管理職は本来の役割を果たせます。
最後に、代替要員の計画を立てておくことも忘れてはいけません。プレイングマネージャーが休んだら現場が止まる、という状態は本人に過度なプレッシャーを与えます。あらかじめ代わりに立てる人材を準備し、仕組みで負荷を分散することが大切です。
プレイングマネージャーは「現場も見られる管理職」であっても、「残業無制限の便利屋」ではありません。法令順守は防御のためだけではなく、プレイングマネージャーが燃え尽きずに活躍し続けるための攻めの基盤でもあるのです。
〇10.部下育成の5つの視点──やる気とやりがいの両立
プレイングマネージャーの最大の仕事は、「部下を育てること」です。目先の成果を自分で背負い込みすぎると、やがて疲弊し、チーム全体の成長も止まります。反対に、人材の育成に意識を向けると、部下が自走できるようになり、プレイングマネージャー自身も余力を確保できます。
では、具体的にどのように部下を育てればよいのでしょうか。ここでは5つの視点を紹介します。
①任せ上手になる
まずは「任せる」という設計が必要です。ただ仕事を渡すのではなく、「この成果をあなたにお願いする」と結果責任で切ることが大切です。その際、レビューの頻度や評価の基準を先に共有しておくと、部下も安心して動けます。
②経験や体感で示す
部下は理屈だけでは動きません。自分の体験をもとに「こんな状況で、こんな行動をとり、こういう影響があった」と具体的に語ることで説得力が増します。成功例だけでなく、失敗の話も正直に伝えることが学びになります。
③現場を過度に恐れない
現場からの異論や批判は必ず出てきます。これを「期待の裏返し」ととらえることで、対話のチャンスに変えられます。むしろ反発があるのは、現場が動いている証拠です。恐れず受け止めて、期待値を再調整しましょう。
④現在ではなく未来の課題を考える
育成は「今うまくいっているか」だけでなく、「半年後・一年後にどうありたいか」から逆算して考える視点が必要です。未来像を思い描いたうえで、今すぐ着手すべきことを二、三決めて実行するようにすると、無理なく成長につなげられます。
⑤失敗から学ぶ習慣をつける
失敗を避けるのではなく、どう活かすかが重要です。「What(何が起きたか)」「So what(なぜ重要か)」「Now what(次にどうするか)」の流れで事例の振り返りを習慣化すれば、学びをチーム全体の財産にできます。
こうした育成の姿勢は、単に部下を成長させるだけでなく、プレイングマネージャー自身を楽にします。自走できる人材が増えれば、プレイングマネージャーは管理に集中でき、現場の風通しもよくなります。そして会社全体としても「やる気とやりがいを両立できる職場」が形づくられ、持続的な成長につながっていくのです。
そして、ここに書いた5つの例はあくまでも、人材育成の最初のステップ(スモールステップ)です。プレイングマネージャーの立場に立った時、いかに部下たちとコミュニケーションを取り、現場を管理・統括できるか、そして成長させていけるかが、その仕事の醍醐味であると言っても良いでしょう。そこでは、「やる気」と「やりがい」が直結して、プレイングマネージャーが陥りがちな「空回り」や「疲弊」を避けることができるのです。
〇おわりに
いかがだったでしょうか。
中小企業のみならず、プレイングマネージャーをいかに育成し、それを現場にも敷衍していくのかということは、会社の今後の方向性をも左右しうる課題だということが見えてきたと思います。要は、プレイングマネージャーを「仕事に精通した管理者」としてだけとらえるのではなく、企業の骨格として見据えていくことがポイントとなります。
欧米の例では、『マインクラフト』の開発者であるマルクス・ペルソンがプレイングマネージャー的な職務を好んで選んだ、という例なども紹介しましたが、これは稀な例です。一方、日本ではスポーツ界の古田敦也さんをはじめとして、プレイングマネージャーとして活躍している人が多くいます。
こうしたことは、文化的な側面のみならず、法制度によっても影響されています。プレイングマネージャーを便利な駒としてあつかってしまえば、法律に触れるリスクが生じますし、何よりもPM自身が疲弊してしまい、会社の骨格が揺らいでしまうのです。中小企業にあってかつてはプレイングマネージャーの地位にあった経営者であれば、「PMそのものを育てる」という視点を忘れてはならないでしょう。
このように、プレイングマネージャーとは日本という風土のなかで育ってきた、貴重な役職であると言えます。肩書きとしては「管理職」、でも「現場」でも一流──そのようなプレイングマネージャーは貴重ですが、過度の「現場での成果」にこだわることなく、部下を安心して任せられる、この人の下に人材をおけばきっと育ってくれる、といった見通しを持つということが、まず一番に大切なのです。

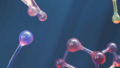

コメント