- 〇はじめに
- 〇第1章 クオリアとは何か──科学では説明できない不思議なこと
- 〇第2章 クオリアとは?──脳に流れ込む感覚のインプット
- 〇第3章 個性とは?──世界に表れる行動のアウトプット
- 〇第4章 クオリアは個人の行動(個性)にどれくらい影響を与えるか?
- 〇第5章 クオリアの個人的な差について──コーヒーの味の違いはクオリアによるものか?
- 〇第6章 文化がクオリアに与える影響──男は黒で、女は赤?
- 〇第7章 脳科学的や神経医学の知見からクオリアを考える
- 〇第8章 哲学的な知見からクオリアを考える
- 〇第9章 クオリアは個人を図る一つのマイルストーン(指標)になりえる
- 〇第10章 機械(AI)と人間の違い。──クオリアは単なる情報ではない
- 〇おわりに
〇はじめに
「ねえ、このコーヒー甘い」
「えっ? ミルクも砂糖も入れていないよ? わたしには苦く感じられるけれど?」
「そうなの? わたしにはとっても甘いけれどなあ……」
皆さんは、日常でこうした経験をしたことはないでしょうか? あるいは……
「ねえ、このリンゴの色、何色に見える?」
「え? 赤でしょう?」
「その赤って、どんな色?」
「うん。燃えるような、なんだかあたたかい色」
「わたしには、海の色に近い落ち着いた色に見えるけれどなあ……青というか緑というか」
みなさんは不思議に、あるいは当たり前に思われるかもしれませんが、こんなことも日常的に起こりえます。これは、一見「感性」や「個性」の違いのようにも思えますが、その底には「クオリア」の違いが関係しているかもしれません。
クオリアとは哲学や脳科学の用語ですが、もともとはラテン語の「qualitas」あるいは「qualis」を語源としている言葉で、「感じられる質」とか「生々しい質感」といった意味を持っています。
ある人と別の人とで、「リンゴの色」や「コーヒーの味」がまったく別のもののように感じられる……そうしたものは、現在では、単に個性や感性の違いによるだけでなく、クオリアの質の違いによるものとも考えられています。
では、このエッセイではみなさんに「クオリア」とは何なのか、「個性」とはどのように違うのかを解説していきましょう。哲学、科学……とくに脳科学や神経医学、精神医学、などの分野でクオリアとはどのように考えられているかも、詳しく解説しています。
〇第1章 クオリアとは何か──科学では説明できない不思議なこと
私たちはふだん何気なく「リンゴは赤い」と言います。でも、もしかするとあなたが見ている赤と、私が見ている赤はまったく違う色なのかもしれません。誰にも確かめようのない「感じの質」、それこそがクオリアと呼ばれるものです。……たとえば、同じメロディーを聴いても懐かしさを感じる人もいれば、胸が苦しくなる人もいる。クオリアとは、そうした個人の内側に宿る独特の感覚の質を指しているのです。
この言葉を最初に使ったのは、アメリカの哲学者クラレンス・アーヴィング・ルイスでした。1929年に出版された『精神と世界の秩序』のなかで、彼はクオリアという概念を提示します。
その後、彼の教え子であるネルソン・グッドマンや、意識の問題を深く掘り下げたトマス・ネーゲルらによって、この考えはさらに発展していきました。1950年代から1970年代にかけて、哲学の議論のなかで「クオリア」という言葉は徐々に浸透していったのです。
なかでも有名なのが、ネーゲルの思考実験「コウモリであるとはどのようなことか?」です。人間がコウモリのように翼をもち、超音波で外界を知覚できるようになったとしても、果たして「自分はコウモリだ」と実感できるでしょうか? つまり、クオリアとは「その存在として生きる」ことの体感であり、人間は結局、人間のまなざしでしか世界を理解できないという限界を示しているのです。この問題は、意識研究における「意識のハードプロブレム」とも直結します。
そして現在では、脳科学者の茂木健一郎氏などが、クオリアに関する活発な議論を展開しています。
科学が情報処理や神経活動を解き明かしても、「感じる」という質そのものを説明することはできません。さらに、人間だけでなく動物たちも独自のクオリアを持っているのではないかと考えられています。
生物学者ユクスキュルが提唱した「環世界」という概念は、動物ごとに異なる知覚の世界があることを示しています。犬の嗅覚の世界、鳥の視覚の世界──それぞれに固有のクオリアが広がっているのです。
こうして見ると、クオリアとは科学(とくに脳科学)だけでは解けない「不思議の入口」です。人間の意識の深みに触れると同時に、あらゆる生命の生きられた世界を尊重するための鍵となっているのです。
〇第2章 クオリアとは?──脳に流れ込む感覚のインプット
クオリアを理解するためには、まず人間の脳がどのように感覚を受けとめているのかを知る必要があります。
私たちの身体には、目、耳、鼻、舌、皮膚といった感覚器官があり、それぞれが外界の刺激を電気信号に変えて脳へと送り届けています。
脳はその電気信号を一定のルールに従って組み合わせ、まとめ上げるのです。そして、まさにその「とりまとめ」の過程から、はじめてクオリアが生まれてきます。つまり、目や舌が直接「赤い」「苦い」と感じているのではなく、脳が情報を整理し統合することによって、私たちはその質感を体験しているわけです。こうした理解のあり方は「身体性」あるいは「身体的認知」とも呼ばれます。
具体的な例を見てみましょう。「リンゴが赤い」という視覚情報、「コーヒーが苦い」という味覚情報、「水仙の香りが心地よい」といった嗅覚情報──これらはいずれもクオリアです。特に香りや味は、個人によって大きな違いが出やすい分野です。同じコーヒーを飲んでも、ある人には深いコクが心地よく感じられ、別の人にはただ苦くて飲みにくいものに感じられることもあります。さらに「本や映画に感動する」といった心の動きもまたクオリアに含まれます。つまり、クオリアとは脳に流れ込んだ外界の情報が「質感」として立ちあらわれる現象であり、私たちの内面を彩るインプット情報なのです。
ただし、クオリアは一度決まったままのものではありません。経験や学習によってその感じ方は変わる可能性があります。たとえば、子どものころは苦手だった野菜が、大人になると好物に変わることがあります。これは味覚をつかさどる神経だけでなく、その背景にある経験や記憶がクオリアに影響を与えていることを示しています。
さらに現在の脳科学によれば、外の世界に働きかけるような「外向きのクオリア」が存在するのではないか──という仮説も提案されています。
重要なのは、脳が外界をどのように理解しているかは科学的に観察できても、「それが脳自身にはどう感じられているか」は検査や理論では決して明らかにできない、という点です。
このギャップこそがクオリア研究を難しくし、同時に魅力的なものにしています。認知科学や脳科学の最前線では、この謎に少しでも迫ろうと多くの試みが行われています。また、クオリアは先天的な神経構造だけで決まるわけではなく、遺伝子の影響に加え、人生のなかで積み重なる経験にも大きく左右されているのです。
〇第3章 個性とは?──世界に表れる行動のアウトプット
クオリアがよく混同されやすい言葉に「個性」があります。しかし、両者は似ているようでまったく別のものです。クオリアは脳科学や認知科学の分野で語られる、内面的な「感じ方の質」を指します。一方、個性というのは心理学や社会学、哲学などで扱われる、外にあらわれた「その人らしさ」を指します。
別の言い方をすれば、クオリアが「インプット」されるものだとすれば、個性は「アウトプット」されるものです。……こうした言い方でよく分かる方もいるかもしれませんね。パソコンに入力する、パソコンから出力される、それぞれのデータを見てみてば、インプットではそれはパソコンに受け取られるものであり、アウトプットであればそれはパソコンから出てくるものなのです。
そして、これが大事なポイントですが、個性がない人がいないように、クオリアがない人もいません。誰もが何かを感じ、そして何らかの行動をとる──この両方がそろって、私たちは人間らしく生きているのです。
では、個性とはどのように表れるのでしょうか?
たとえば、華やかな服を選ぶ人もいれば、落ち着いた色の服を好む人もいます。朝ごはんに和食を選ぶ人もいれば、パンとコーヒーが欠かせない人もいます。人と話すときに、控えめに言葉を選ぶ人もいれば、陽気に冗談を交えながら会話を楽しむ人もいるでしょう。
こうした態度や選択の積み重ねが、その人の個性を形づくります。つまり、個性とは脳のなかで考えたことが外の世界に出てくるときの「表情」であり、世界との接点に立ちあらわれるものなのです。
個性はまた、生物学的にも重要な意味をもちます。同じ群れのなかで、一頭一頭を見分けるためには、姿かたちや行動の特徴がはっきりと見分けられることが必要です。ある個体が群れのリーダーとなるのは、主にその個性や力が周囲から信頼や魅力として認められるからです。つまり、個性があるということは、個体が社会的な役割を果たすうえで不可欠な戦略でもあるのです。
人間においても同じです。個性は人と人とをつなぎ、時には対立させ、そして社会を形づくります。進化心理学では、個性の多様さは集団全体が環境に適応するための仕組みだと考えられています。控えめな人と積極的な人が同じ社会にいることで、群れとしての生存戦略が豊かになるのです。
このように見ていくと、個性とは、クオリアとは違って、外の世界に直接触れる「行動の姿」だと言えます。感じ方の質としてのクオリアが土台となり、その土台から世界へと表現されるものが個性なのです。
〇第4章 クオリアは個人の行動(個性)にどれくらい影響を与えるか?
これまで見てきたように、「クオリア」は脳に備わった感覚的なはたらきであり、「個性」はそれが外の世界に表れる心理的・社会的な動きです。一見すると、両者は別々のものに見えますが、実際にはとても深く結びついています。人が成長していくなかでクオリアが変化し、それが行動や個性の形に影響するという例も知られています。
たとえば、色覚に違いがある人を考えてみましょう。
色盲の人の場合、まったく色を判別できないこともあれば、特定の色の区別がつきにくい場合もあります。典型的なのは赤と緑の見分けがつかないケースです。この場合、私たちが「リンゴは赤い」とごく自然に思うとき、その人には「赤」というクオリアがまったく異なる「緑」に近いような質感で見えているのです。
その違いは、日常の行動にも表れます。たとえば信号機の赤と青(緑)を見分けるとき、他の人には簡単でも、色盲の人にとっては判断に工夫が必要になります。つまり、クオリアの質の違いが、そのまま行動や個性に影響を与えるのです。
医学や精神医学の分野でも、クオリアはしばしば注目されます。ある医師は「意識とはクオリアのかたまりである」と述べ、精神症状との関係を指摘しました(*1)。離人感と呼ばれる、自分や外界がどこか現実味を失って感じられる症状は、外界を認知する際のクオリアがうまく働かないためではないか、とも考えられています。統合失調症に見られる幻覚や幻聴といった症状も、クオリアの異常が背景にある可能性があると語られています。
心理学の研究でも、クオリアの影響は無視できません。ある研究者は「僕らは他人と同じ経験をすれば、同じクオリアを感じているはずだと思い込んでいます。しかし同時に、他人と自分は経験をまったく共有できないとも思い込んでいます」と述べています(*2)。つまり、クオリアの違いは客観的に比べることができず、人と人との間でどのように質感が伝わっているのかを識別することは非常に難しいのです。
このように見てくると、クオリアは単に感覚の質を示すだけでなく、私たちの行動や感情、さらには病気や社会生活のあり方にも影響を及ぼしていることが分かります。クオリアとは、ひとりひとりの世界の見え方を決定づけ、その人らしい生き方を形づくる根源的な要素なのです。
(*1)「クオリアと精神医学」城間クリニック 城間清剛
https://archive.okinawa.med.or.jp/old201402/activities/kaiho/kaiho_data/2006/200607/pdf/087.pdf*2) 「どんなクオリアにも「構造」がある──モナシュ大学教授・土谷尚嗣が語る意識研究の最前線」モナシュ大学教授 土谷尚嗣

〇第5章 クオリアの個人的な差について──コーヒーの味の違いはクオリアによるものか?
私たちが日常でよく口にするコーヒーは、クオリアの個人的な差を考えるうえでとても身近な素材です。同じコーヒーを飲んでも、「苦くて飲みにくい」と感じる人もいれば、「ほどよい苦味が心地よい」と感じる人もいます。あるいは、砂糖やミルクを入れなくても「甘みがある」と表現する人さえいます。ここには、単なる好み以上の、クオリアの違いが表れているかもしれません。
この差を整理すると、大きく三つの側面があります。
第一に「クオリア的な側面」です。つまり、脳がどのように味覚を質的に経験しているかということ。
第二に「生理的な側面」です。舌にある味蕾の数や敏感さには個人差があり、その違いが「苦い」「甘い」といった感覚の強さを左右すること。
第三に「経験的・文化的な側面」です。小さい頃からコーヒーを飲んで育った人と、そうでない人とでは、同じ味でも受け止め方が大きく違うということ。
この三つの要素は独立しているわけではなく、互いに重なり合っています。たとえば、苦味に敏感な舌を持っている人や、苦い薬草茶を日常的に飲む文化を持つ地域で育った人などは、苦味を「良い味」として受け止めることもあるでしょう。逆に、甘い果物を日常的に食べている地域の人などは、それを「耐えられないほど苦い味」と感じる可能性もあります。
このように、その人の個人的な経験や文化的背景が、脳のなかのクオリアをも形づくっていくのです。
結論としては、味覚の違いを生むのはクオリアそのものの差であると同時に、身体の生理的な特徴や、生活習慣、文化の影響によって変化する部分も大きいということになります。むしろ、そのような多層的な違いこそが、クオリアの特性を示しているのかもしれません。
近年では、脳科学や認知科学の分野において、脳波や脳活動を測定して、個人ごとのクオリアの違いを探ろうとする試みも始まっています。また、統合情報理論など意識研究の最前線でも、こうした質的な差をどう理解するかが議論されています。科学が進んでもなお、クオリアの謎は深まるばかりです。
そして、第4章で触れた問題もここに関わってきます。ある人が「コーヒーを苦い」と感じ、別の人が「苦くない」と感じる。そのように、各人によってまったく違ったふうにクオリアが感じられることを、「逆転クオリア」と言います。
その差は、習慣や文化に由来する場合もありますが、生まれつき異なるクオリアを持っている可能性も高いのです。私たちは他人の感じ方を完全には知ることができません。けれども、その違いを想像することは、人と人との関係をより豊かにする手がかりになります。クオリアはまさに、個性や感性を形づくるための礎石、とも言えますね。
〇第6章 文化がクオリアに与える影響──男は黒で、女は赤?
日常生活のなかで、私たちは「文化によってかたちづくられたクオリア」に囲まれています。
たとえば、日本の公共トイレを思い浮かべてください。男性用は寒色系──青や黒で表示され、女性用は暖色系──赤やピンクで示されていることがほとんどではないでしょうか。私たちはこの色分けを見て即座に「どちらが男性用か」「どちらが女性用か」を判断します。これは単なる色のクオリアだけでなく、社会が積み重ねてきた暗黙のルール=社会的コードに依拠しています。
ところが、西洋のトイレでは必ずしも「男は黒」「女は赤」とはなりません。文字やシルエットで区別される場合もあれば、色が逆転していることもあります。つまり、色そのものの印象──クオリア──に加えて、それをどう意味づけるかは文化に大きく左右されるのです。赤を「情熱」や「女性性」と結びつける社会もあれば、「危険」「警告」と受け止める社会もある。文化がクオリアにレッテルを貼ることで、同じ赤でも感じ方は大きく変わってしまうのです。
音楽の例も興味深いです。
日本では「ヨナ抜き音階」が心地よい響きとして広く受け入れられています。ヨナ抜き音階とは、ドレミファソラシドから「ファ」と「シ」を抜いた音階で、童謡や民謡、演歌などに多く使われています。この響きは、郷愁や安心感といったクオリアを多くの日本人に呼び起こします。一方、西洋音楽の基盤は、古代ギリシアの旋法に始まり、教会音楽を経て、バロック派やロマン派といった音楽が展開してきました。その後、ケルトやスラブ、ゲルマン、ノルディックなど多様な民族音楽の影響が加わり、独自の「心地よさ」の基準が培われていったのです。
このように見てくると、文化は「感覚の質」に意味を与え、社会的に共有できるかたちに整えているといえます。色や音といったクオリアは本来きわめて個人的な体験ですが、文化的な枠組みのなかで「わかりあえるもの」へと翻訳されていく。だからこそ、私たちは他人と「赤いドレスの情熱」や「懐かしい童謡の音階」を共有し、そこに共感を見いだすことができるのです。
文化がクオリアに与える影響を考えることは、個性が社会のなかでどのように理解され、共有されるのかを知る手がかりになります。そして、世界には数えきれない文化がある以上、クオリアの感じ方もまた無限の広がりを持っているといえるでしょう。
〇第7章 脳科学的や神経医学の知見からクオリアを考える
クオリアは哲学や心理学のほか、脳科学や神経医学、精神医学などの面でも研究されてきました。しかし、その本質は依然として謎に包まれています。最大の理由は、クオリアが「不可視」であることです。心拍や血圧のように計器で直接測定できるものではなく、「私にはこう見える」「私はこう感じる」といった自己申告や、そこから推測するしか方法がないのです。
脳科学の分野でクオリア研究を進めてきた人物として、日本では茂木健一郎氏がよく知られています。
著書『脳とクオリア』や『クオリアと人工意識』では、脳内でニューロンが発火し、シナプス結合を通して複雑に影響し合うことで、豊かな心の質感=クオリアが生じるのだと説明しています。茂木氏は、心の中を「熱帯雨林の生態系」にたとえ、無数の神経活動の相互作用によって独自のクオリアが育まれると述べています。さらに「この一つ一つのクオリアを、私たちの心は混同しようのない個性として捉えている」と語り、質感が人間の精神活動の豊かさそのものを示しているとしています(*3)。
たとえば、神経医学などの分野では、科学技術の進歩でMRIを使えば「脳のどの部分が赤を見ているのか」を調べることができるようになりました。しかし、「赤」がどのように見えているのかまではわかりません。コンピューターで色を表す際には、色相や輝度といった2つのパラメーターで十分ですが、人の感じる「色のクオリア」は、より多くの要素を含む複雑な現象だとされています(*4)。
クオリアの性質を理解するために、身近な例を挙げてみましょう。何年も家を離れていた人が実家に帰ってきたとき、庭や家族の姿が変わっていたとしても、「ここは自分の家の庭だ」「これは自分の家族だ」と感じ取ることができます。これは、外界の物質的な情報をそのまま写し取っているのではなく、クオリアが「同じものを同じもの」「違うものを違うもの」と判別する役割を担っているからです。
つまり、クオリアとは機械的に測れる情報ではなく、私たち一人ひとりの心が体験する「質感」そのものです。脳科学や認知科学、精神医学などで科学的な探究が進んでも、最終的にたどり着くのは「感じるとは何か」という問いであり、そこには計測を超えた人間のこころの世界が広がっているのです。
(*3)「脳とクオリア なぜ脳に心が生まれるのか」茂木健一郎
(*4) 「どんなクオリアにも「構造」がある──モナシュ大学教授・土谷尚嗣が語る意識研究の最前線」モナシュ大学教授 土谷尚嗣

〇第8章 哲学的な知見からクオリアを考える
第7章で触れたように、クオリアは脳科学や神経医学をはじめとした科学で測定できるものではないため、哲学の側からの視点が欠かせません。哲学の歴史を振り返ると、「心は存在しない」とする唯物論、「心と物質は別だ」とする二元論、そして「心と身体は一体だ」と考える物心一元論と、大きく三つの立場が見えてきます。
古代にまでさかのぼれば、アウグスティヌスが「神の国」で語った世界観にその萌芽を見ることができます。新プラトン主義の影響を受け、物質世界という階層の上に精神の世界があるとした彼の思想は、クオリアを含む精神世界を「物質世界よりも次元の高いもの」と位置づける基盤をつくりました。
近代に入るとデカルトが登場し、「我思う、ゆえに我あり(コギト・エルゴ・スム)」と述べることで、精神と身体を切り分ける二元論が鮮明になります。彼の二元論と現代のクオリア研究における二元論は厳密には異なりますが、「意識は主体的な構造である」という点でつながっています(*5)。
さらに19世紀以降は、身体の意味に注目が集まりました。フォイエルバッハやマルクスは、人は他者や自然との関わりのなかで人間となるのだと考えました。マルクスの「自然は人間の非有機的身体である」という言葉は、身体と精神の関係を新たにとらえ直す契機となり、クオリアのような意識や精神の問題を神秘的な次元と結びつけて理解する潮流を生みました(*6)。
20世紀に入ると、メルロー=ポンティが身体と知覚の哲学を展開しました。彼は精神と身体を二項対立としてではなく、互いに溶け合い響きあうものとみなし、人間存在をとらえ直しました。ここにクオリアの考えを重ねると、それは精神的でありながら身体とも共鳴する現象だと理解できます。
そして現代の哲学者チャーマーズは「哲学的ゾンビ」という思考実験を通じて、クオリアの不可思議さを浮かび上がらせました。彼が提示した「意識のハードプロブレム」は、物質世界の情報処理では意識の質感を説明できないことを端的に示しています。クオリアとはまさに、「手に触れられないもの」なのです。
このように、クオリアやそれに類似する考え方は、ある時代には神秘として仰ぎ見られ、ある時代には科学に挑む課題として位置づけられてきました。今日では科学的に「不可視のもの」として再び注目を集めています。人間の個性や行動に現れる違いの奥には、なお測り得ないクオリアの深淵があるのです。
(*5) デカルトの説では「実体二元論」、クオリアを研究している現代哲学では「自然主義的二元論」になる。
(*6) 「頸城野郷土資料室学術研究部 研究紀要 Vol.5/No.3 人(one-self)と自然(another-self)の be 動詞連合」石塚正英
〇第9章 クオリアは個人を図る一つのマイルストーン(指標)になりえる
ここまで見てきたように、クオリアは私たちの個性にも深く関わっている可能性があります。
人はそれぞれ異なる感覚を抱えて生きており、その差は小さなようでいて実は驚くほど大きいものです。例えば、同じレモンティーを飲んでも「ほんのり甘い」と感じる人もいれば、「ちょっと苦い」と思う人もいるでしょう。それは舌の感覚器の違いだけでなく、そもそも感じ取っているクオリアの質そのものが異なっているかもしれないのです。このような状況は「逆転クオリア」の良い例でしょう。
問題はやはり、こうしたクオリアを科学で測ることができないという点です。
脳科学や神経医学の技術で脳波や生理反応を計測しても、その人が実際に「どのように赤を見ているか」「どのように苦みを感じているか」を直接知ることはできません。この不可視性こそが「意識のハードプロブレム」と呼ばれる所以です。測定できないからこそ、クオリアは数値ではなく「尊重すべき個性」として受けとめられるべきなのです。
さらに一部の脳科学研究者は、クオリアには「志向性クオリア」と呼ばれるものがあると指摘しています。これは「コーヒーを飲みたい」「あの人に会いたい」といった欲求や指向性を伴うクオリアのことです。ただし、静的に感じる色や音と同じカテゴリーに入れて良いのかどうかは、まだ議論の余地があります。
結局のところ、クオリアは外からラベルを貼って分類するための「指標」ではありません。むしろ、その人の内面に寄り添うための「詩的なマイルストーン」、すなわち「こころの道しるべ」と呼ぶのがふさわしいのかもしれません。数値や理屈で扱うのではなく、温かく見守り、尊重する対象として存在しているのです。
クオリアは、人間や(一部の)動物がそれぞれにもつ「独自の世界の現れ」と言えるでしょう。その理解はまだ始まったばかりであり、尽きることのない問いのかたちで、これからも私たちの前に立ち現れ続けるはずです。そして、その永遠に手の届かない不思議さこそが、クオリアというものの魅力の源泉なのです。
〇第10章 機械(AI)と人間の違い。──クオリアは単なる情報ではない
近年、ChatGPTやGemini、Copilot、Claude、PerplexityといったAIがさまざまな分野で活躍し、人間に近い自然な会話をこなす姿を目にする機会が増えてきました。そのため、「AIに心やクオリアはあるのだろうか」という問いがしばしば話題にのぼります。確かに、AIと対話していると「人間らしい」と感じる瞬間があります。しかし、その内実は精緻な情報処理の結果にすぎません。
たとえば、「こんにちは」と声をかけると、AIが「こんにちは。今日は病院の帰りですか?」などと返すことがあります。これは相手を気遣っているように聞こえますが、実際には以前の会話を参照し、関連性の高い返答を組み立てているに過ぎません。残念ながら、そこに「心からの思いやり」があるわけではないのです。
一方で、人間の意識や心については、古くから哲学や科学で議論が続けられてきました。近年では「量子脳理論」という仮説が注目されることもあります。これは脳内の微細な構造が量子力学的にふるまい、外界との相互作用を通じて意識やクオリアが生まれているのではないか、という考え方です。人間以外にも、哺乳類やタコ、イカのように高度な神経系を持つ生物には、クオリアが存在する可能性があるとされています。
しかし、機械にはそのような器官がありません。AIは人間のように情報を「考える」ことはできますが、「どう感じたか」を持つことはできません。デカルトが述べた「我思う、ゆえに我あり(コギト・エルゴ・スム)」を借りるなら、AIが備えているのは前半の「我思う」にあたる部分だけであり、その先にある「我あり」という実感を持つことはないのです。
AIが心や意識を持つことを恐れる人もいれば、期待する人もいます。未来のAIが人間と似たような光を宿すかどうかは、技術の進歩の方向性と、人間がどんなふうにAIに接していくのかによって変わってくるでしょう。現時点でクオリアを確かに持つのは人間だけだと考えられます。しかし、それでもAIが担っている「考える営み」は確かに存在します。意識や心ではなくとも、それはひとつの「コギト」と呼ぶにふさわしい働きなのです。もしかしたら、AIにとってはそのコギトこそが個性なのかもしれません……。
〇おわりに
いかがだったでしょうか。みなさんも「クオリア」という言葉の意味にふれて、なんとなくその考えというものが分かってきたのではないでしょうか。なかには、人によって感じる質感が違う、「逆転クオリア」という興味深い例もありました。
クオリアとは、繰り返しになりますが、心のなかで感じられるなんらかの「質感」や「感触」のことです。それは、脳にむかって内向きにインプットされるときに表れてくるもので、個性とは異なります。個性とは、個人の言動や感情としてあらわれる、外向きのアウトプットに関係しているものだからです。
「コーヒーの味の違い」「リンゴの色の違い」「映画を見てどんなふうに感じたか」そうしたことは、現在では個人個人のクオリアの違いが関係しているのではないか、と言われています。そして、このクオリアは科学では決して測定できません。哲学上の難しい問題として横たわっているものが、クオリアなのです。
クオリアは個人の言動や感情に影響することもあります。例えば、色盲の人は自動車を運転している際に信号を見分けにくかったり……そのことで運転が慎重になる、ということもあり得るでしょう。また、ある食べ物やメニューを好んだり好まなかったり、ということも起こりえます。
この文章は、決して難解なものではなく、かみくだいて読んでいけば、みなさんにもクオリアというものがどういうものなのかが自然とわかってくるでしょう。そして、クオリアとは現在でも哲学、科学、医学などの分野で果てのない研究対象としてさまざまに考察されているのです。
この小論ではクオリアの奥深さまでは説明することはできませんでしたが、みなさまがクオリアというものを感じ、考え、そしてそれがもう一つの「個性」であると納得していただけたら、幸いだと思います。そして、現在話題になっているAIの問題──未来においてはAIもクオリアを持つようになるのかもしれない……そんなことにも思いを馳せてみてはいかがでしょうか?
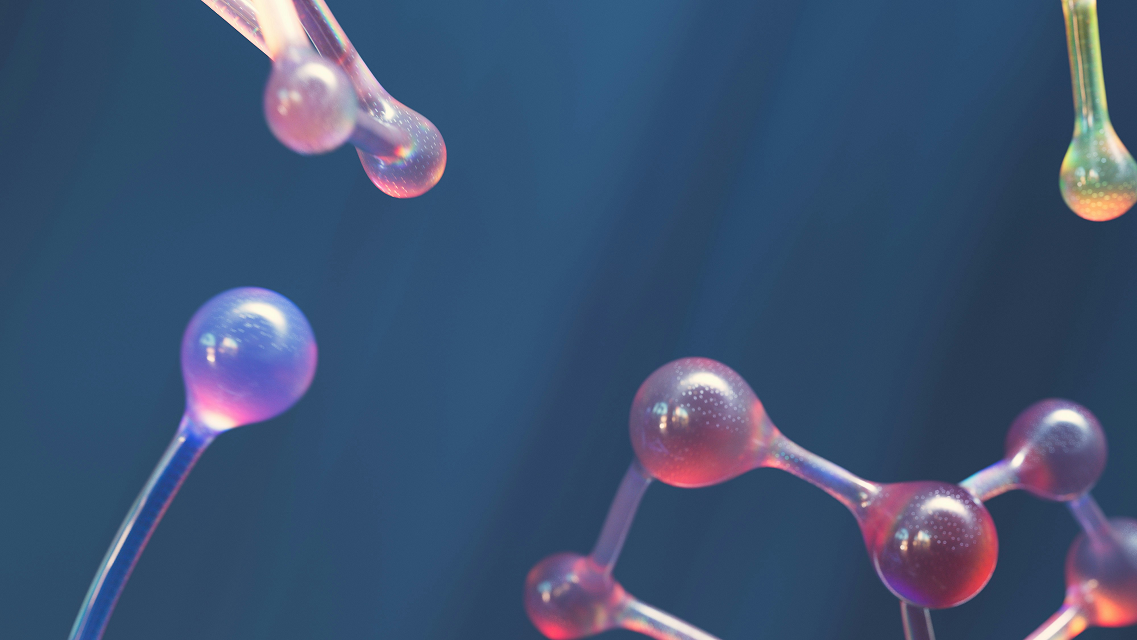
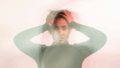

コメント