- 〇はじめに
- 〇第1章:世代間ギャップ──沈黙の壁と見えない距離
- 〇第2章:世代間ギャップの構造──時間が生む価値観のズレ
- 〇第3章:人見知りの正体──関係性構築によこたわる最初の壁
- 〇第4章:原因を探る──なぜギャップは生まれるのか
- 〇第5章:事例で見るギャップ──現場の声から
- 〇第6章:沈黙の哲学──話さないこともまた関係性
- 〇第7章:ハラスメントと距離感──善意がすれ違うとき
- 〇第8章:コミュニケーションの再設計──世代を越える対話の技術
- 〇第9章:制度と文化──組織ができること
- 〇第10章:世代間ギャップを解消するための研修会──いかに意識を高めるか?
- 〇第11章:将来への展望──ギャップを越えて、関係を編む
- 〇おわりに
〇はじめに
若者は年長者の言うことを聞かない。そして、年長者は若者の気持ちや思いをわかってあげられない。──その結果として、若者の側からも年長者の側からもコミュニケーションを取る機会が減ってしまい、会話や応対にどんどんずれが生じていってしまう。そうしたことが「世代間ギャップ」の本質であると言えます。
世代間ギャップは意外にも古くて新しい問題で、古代エジプトの壁画などにもその様子が記されていたと言います。
「世代間ギャップ」は「ジェネレーションギャップ」とも呼ばれますが、歴史的にみると、アメリカではヒッピー世代が台頭しはじめた1960年代から、日本では第二次ベビーブームの子供たちが成長期にさしかかった1970~1980年代から、さかんに使われ始めたと考えられています。
最近の例で言えば、たとえば「8時10分前に集合」という表現について、多くの年長者は「7時50分」のことだと考えたのに対して、若者世代では「8時10分のすこし前」ととらえた人が多かったことなども、調査の結果から分かっています。このように、世代間ギャップとは仕事や家庭におけるさまざまな場面において、今も昔も、解決が難しい問題として存在しているのです……。
このコラムでは、世代間ギャップ(ジェネレーションギャップ)の本質や原因についてあらためて考察してみることで、この問題を解決・解消するための手掛かりを探っていきたいと思います。人見知りなどの性格が原因なのかどうか、研修や事前の準備などによってそれを解決できるのかどうかについても解説しています。
〇第1章:世代間ギャップ──沈黙の壁と見えない距離
職場でちょっとした会話が弾まない、あるいは「なんとなく相手との距離を感じる」──そんな経験をしたことはありませんか? 会話する相手が上の世代であれ下の世代であれ、声をかけづらい空気が生まれてしまうことは、多くの人に共通する悩みです。その原因のひとつに「人見知り」的コミュニケーションがあります。
人見知りというと、個人の性格の問題のように思われがちですが、実際には世代をまたいだ関係性のなかで強まることが少なくありません。話題が合わないかもしれない、誤解されるかもしれない、あるいは「余計なことを言ってしまうかも」という不安。これらが無意識のブレーキになり、世代間の沈黙を生み出してしまう原因になるのです。
こうした現象を一般的に「世代間ギャップ(ジェネレーションギャップ)」と呼びます。
この言葉自体は決して新しいものではありません。時代ごとにその意味合いを変えながらも、昔から「親世代と子世代の間に横たわるもの」として受け継がれてきました。現代では、単なる価値観の違いを示すだけでなく、コミュニケーションのあり方そのものを映し出すキーワードになっています。働き方が多様化し、職場に複数の世代が同時に在籍するようになったことで、世代間の「見えない壁」は、より意識されるようになりました。
ですが、この問題は簡単には解決されません。……たとえば会議のあと、上司世代が雑談を始めても、若手は相づちを打つ程度で会話に入ってこない。逆に若手同士の会話が盛り上がっても、ベテラン社員は「どう話しかければいいのか……?」と一歩引いてしまう。こうしたシチュエーションは特別なケースではなく、日常のなかで誰もが目にする「あるある」の一コマです。
このような小さな沈黙や躊躇の積み重ねが、世代間の距離を広げていきます。けれども、それは必ずしも「個人の努力不足」を示しているのではありません。むしろ、人見知りや遠慮が世代間の関係にどう作用するかを理解することが、人同士のあいだに横たわる関係性を築き直し、世代間ギャップを解消する第一歩になるのです。
〇第2章:世代間ギャップの構造──時間が生む価値観のズレ
「世代間ギャップ」という言葉が広く使われ始めたのは、実は半世紀以上も前のことです。日本の場合、高度経済成長期に親世代と子世代のあいだに生活習慣や価値観の大きな違いが生まれ、それをアメリカの事例にならって「ジェネレーションギャップ」と呼んだのが始まりでした。当時は、音楽やファッション、恋愛観の違いが主な対象でしたが、時代を経てその意味合いは広がり、いまや職場や家庭のあらゆる場面に浸透しています。
現在の職場では「昭和世代」と呼ばれる上の世代と、「Z世代」と呼ばれる若者世代が同じ空間にいることも珍しくありません。昭和世代が「我慢して働くことが美徳」と考える一方で、Z世代は「効率よく働き、プライベートを大事にすることが当然」と考える。このように、世代ごとに形作られた価値観は、単に考え方が違うのではなく、育った時代背景が作り出した「構造的なズレ」を含んでいるです。
例えば、残業への姿勢を見ても違いは明らかです。上の世代には「皆が残っているのに自分だけ帰るのは気が引ける」という意識が強くあります。ところが若手の世代は「必要な仕事が終わったなら、早く帰って自己研鑽や休養にあてるのが合理的」と考えます。このズレが起きる原因は、個人の性格の違いというよりも、時代が生んだ働き方の「常識」の違いにあると言えます。
また、プライベートの扱い方にも違いが出ます。昭和世代は「会社は家族のようなもの」という考え方が根強く、休日の過ごし方や家庭の話題まで共有することを自然なものと考えがちです。一方でZ世代は、仕事と私生活をきっちり分け、「プライベートは尊重してほしい」と望みます。どちらが正しいわけではなく、それぞれの時代にとっては当然の価値観だということなのです。
こうした価値観のズレは、意識しないと「相手が冷たい」「自分を理解してくれない」といった心理的距離感につながります。つまり、世代間ギャップは単なる誤解の産物ではなく、時代を背景にした「構造的な違い」が土台にあるのです。このように問題が起きた原因を適切に探っていくことができれば、次世代のコミュニケーション改善への入口になります。
〇第3章:人見知りの正体──関係性構築によこたわる最初の壁
「人見知り」という言葉を聞くと、どうしても単なる性格の一部だと考える人も多いのではないでしょうか。
しかし心理学や精神医学の観点から見ると、それは単なる「恥ずかしがり屋」的な性格ではなく、人間関係を築く際の自然な防衛反応が原因だと説明されます。知らない相手に出会ったとき、人は無意識に「この人は自分にとって安全だろうか?」と判断します。その慎重さが強く表れた状態が、人見知りなのです。
この特性は、世代間のやりとりではより顕著になります。世代が違えば、使う言葉や常識が異なり、「自分の話が通じないかもしれない」という不安が増幅されます。若い世代は「何を言っても変だと思われるのでは?」と感じ、上の世代は「逆に、若者にどう話しかければよいのかわからない」と尻込みする。……こうして双方が互いに距離を取り、人見知り的な反応が強まり、結果として世代間ギャップの解消を難しくしていってしまうのです。
人見知りはまた、関係の築き方の違いとも関連しています。たとえば会社でのベテランにあたる昭和世代にとっては、長い時間を共有しながら少しずつ信頼を積み上げるのが自然でした。一方でZ世代は、SNSやオンラインでの交流を通じて、短い時間でも一気に距離を縮めることに慣れています。どちらも「関係を築く」ことに変わりはありませんが、そのプロセスの違いが、世代間のすれ違いを助長する要因となります。
さらに現代の職場では、「心理的安全性」が十分に確保されていないことも影響しています。心理的安全性とは、「自分の意見を言っても否定されない」「失敗しても責められない」と感じられる状態のことです。こうした雰囲気やルールが欠けていると、人は余計に発言や行動を控え、人見知りの傾向が強くなってしまいます。世代の違いと心理的な不安が重なると、沈黙や遠慮が一層深まり、関係構築の初期段階で断絶が起きやすくなるのです。
つまり人見知りは、世代間ギャップを単に表面化させるのではなく、それを拡大させる「増幅器」のような役割を果たしているのです。誰でも人との違いを意識することは当たり前なのですが、そこに「自分が生きた時間」というものを持ち込むことで、その差異がよりいっそうはっきりしたものになるわけです。この仕組みを理解することが、世代をこえたコミュニケーションを構築していくための最初の一歩になります。
〇第4章:原因を探る──なぜギャップは生まれるのか
ここまで見てきたように、「人見知り」は世代間ギャップを強める大きな要素のひとつです。しかし、それだけが世代間ギャップの原因ではありません。実際には、いくつもの要因が絡み合うことで「世代間の壁」が形づくられていきます。
まず大きいのは、言語や価値観の違いです。
たとえば一つの言葉をとっても、世代によってニュアンスが異なることがあります。若い世代にとってはカジュアルな言い回しでも、上の世代には軽率に響いてしまう。逆に、ベテラン世代が使うビジネス用語が、若手には堅苦しい印象を与える。そうした言葉の背後にある価値観や経験の違いが、そのまま世代ごとの誤解や摩擦につながるのです。
次に挙げられるのは、経験の差です。
長い社会経験を積んだ世代は「成功も失敗も時間をかけて学ぶべき」と考える傾向があります。一方で若い世代は、インターネットやデジタルツールを活用し、効率的に学び、目の前の課題を解決することを重視します。どちらも合理的な考え方ですが、方法の違いが「価値観の衝突」として表面化するのです。こうした傾向は、AIが一般化した現代にあっては、より強まってきていると見て良いでしょう。
さらに、見逃せないのがハラスメントの認識の違いです。
昭和世代が「ちょっとした励まし」と考えていた言葉や行動が、若い世代には「パワハラ」などと受け止められることがあります。逆に、若手世代の軽い冗談が、年配の社員には「礼儀を欠いた発言」と感じられることもあります。ここには、「時代ごとに変わる社会的な基準(標準的な常識)」が関係しており、誰が悪いという単純な問題ではないのです。
そのほかにも、働き方や生活リズムの違いも原因となります。フルタイム勤務を当たり前とする世代と、副業やリモートワークを前提にするZ世代とでは、同じ「仕事観」を共有するのが難しいことがあります。休み方や余暇の過ごし方に対する考え方の差も、距離感を広げる要素になります。
つまり、世代間ギャップの原因は「人見知り」に限らず、言葉、価値観、経験、そして社会的ルールの変化など、複数の要因が積み重なった結果なのだと言えます。その全体像を理解することこそが、次に考えるべき「具体的な解決策」を探るための入り口になります。
〇第5章:事例で見るギャップ──現場の声から
世代間ギャップは抽象的な話だけではありません。実際の現場で、ちょっとしたやり取りが誤解や摩擦につながることがあります。ここでは架空の例をもとに、失敗と成功の両面を見ていきましょう。
ある企業での出来事です。
──新入社員のAさん(Z世代)は、定時で退社する際に「今日はお先に失礼します!」と明るく声をかけました。しかし上司のBさん(昭和世代)は、「まだ周囲が仕事をしているのに、自分だけ早く帰るのか!」と心の中で不満を募らせました。Bさんにとっては「皆で残業するのが当たり前」という価値観があり、Aさんの行動は協調性に欠けるように映ったのです。一方、Aさんにとっては「仕事が終わったら帰るのが当然」であり、むしろ挨拶をすることで誠意を示したつもりでした。両者の価値観の違いが、無言のわだかまりを生んでしまったのです。
……この例では、「お互いが誠意を示しているつもりなのに、それが受け入れられない」というジレンマが顔を出しています。やはり、ここにも「世代間の常識の違い」が表れているわけです。
一方で、同じ会社の別の場面では成功例もありました。
──会議中、若手のCさんがSNSで得た情報をもとに新しい提案をしました。年配のD課長は当初「ネットの情報なんて信用できるのか?」と思いましたが、まずはCさんの話を最後まで聞くよう心がけました。その後、自身の経験を踏まえて質問や補足を加えることで、議論は建設的に進みました。結果的に提案は改善され、プロジェクトの方向性が広がったのです。Cさんは「きちんと耳を傾けてもらえた」と感じ、D課長は「若手の柔軟な発想は侮れない」と学びました。世代を越えた歩み寄りの好例といえるでしょう。
……この例では、D課長が「いったんは自分の考えを白紙にする」と、一呼吸置いたことが成功につながりました。このように、世代間ギャップを解消するためには、「どちらから」というこだわりをなくすことが一番大切なのだと言えます。
ただし、ここで注意したいのは「どこからが(上司や部下に対する)ハラスメントになるのか?」という境界線です。善意のつもりで放った一言が、相手にとっては圧力や干渉と受け止められることもあります。世代間ギャップにおける誤解の多くは、この境界線の見極めが難しいことから生まれるのです。だからこそ、事例を共有し合い、違いを理解する姿勢が欠かせません。
〇第6章:沈黙の哲学──話さないこともまた関係性
世代間のすれ違いを語るとき、どうしても「会話の不足」や「発言のズレ」が注目されがちです。しかし、実は沈黙そのものにも意味があります。人は何も語らないときでさえ、知らず知らずのうちに相手との関係を築いているからです。
「人見知り」を単なる性格と捉えるのではなく、文化的・世代的な現象として見直してみると、問題の解決への糸口が見えてくるかもしれません。
……日本社会では古くから、「沈黙は金」という言葉があり、言葉を控えることに価値を見いだしてきました。とくに上の世代にとっては、口数が少ないことは「思慮深さ」や「謙虚さ」を表す場合もあります。一方で、SNSなどで即時的なやりとりに慣れた若い世代には、「沈黙=関心がない」と感じられることが多いです。つまり沈黙の意味そのものが、世代によって大きく異なっているのです。
沈黙には二つの側面があります。
ひとつは、距離を広げてしまう「沈黙」。会議で何も発言しないことで「意見がない」と受け止められ、関係が浅いままで終わってしまう沈黙です。もうひとつは、距離を縮める「沈黙」。たとえば休憩時間に言葉を交わさなくても、同じ空間を共有することで安心感や信頼が生まれる場合があります。
このように、沈黙には「断絶」と「共鳴」の両方の可能性が含まれているのです。
哲学の視点から見ると、沈黙は「言葉にしない関係性」の表現でもあります。哲学者メルロー=ポンティは、「言葉の合間に含まれる意味の豊饒さ」について、「沈黙の声」という呼称を与えました。つまり、言葉を介さなくても相手の存在を感じ取り、そこに関係を見出すという考え方です。これは若者とベテランの間など、世代間のギャップを解決するための重要なヒントになります。
私たちはつい「話さなければ関係は築けない」と考えがちです。しかし、沈黙もまた立派なコミュニケーションの一部です。沈黙を恐れるのではなく、その背景にある世代ごとの文化や価値観の違いを理解すれば、沈黙の時間さえも関係を育てる場へと変えることができるでしょう。
〇第7章:ハラスメントと距離感──善意がすれ違うとき
世代間ギャップが深刻化すると、単なる誤解では済まされず、ハラスメントとみなされることがあります。これは個人の関係性だけには終わらず、法的な解決を待たなければいけない問題へと発展するリスクをはらんでいます。職場での人間関係が訴訟やコンプライアンス違反に結びつく可能性を考えれば、「自分は善意で言っただけ」という言い分は通用しません。
世代間で異なるのは、まず「どこからがハラスメントか」という認識です。
たとえば昭和世代にとっては「ちょっとした叱咤激励」が、Z世代には「人格否定」として受け止められることがあります。逆に、若手社員が「フランクさ」を意識して取った軽口が、上の世代には「礼儀を欠く侮辱」と映ることもあります。背景にあるのは、育ってきた社会の常識や教育の差です。高度成長期を生きた世代は「努力と根性」が評価されやすかったのに対し、現代の若い世代は「尊重と共感」を大切にする。価値観の軸が異なれば、同じ言葉や行動も全く別の意味に解釈されてしまうのです。
さらに難しいのは、プライベートへの踏み込みです。
昭和世代の上司が「まだ結婚しないの?」と何気なく尋ねるのは、むしろ親しみを込めたつもりかもしれません。しかし若い世代にとっては「個人のライフスタイルに口を出された」と感じ、不快や萎縮につながります。反対に、若手が上司の家庭や健康に関して気軽に質問することで、相手が「プライベートを詮索された」と受け止めることもあります。ここにも世代間の距離感のズレが表れています。
では、どうすれば良いのでしょうか? 鍵になるのは予防と対話です。まず組織として、ハラスメントに関する明確なガイドラインを設けること。そのうえで「どこからが不快に感じられるのか」を、世代を超えて率直に話し合える環境を整えることが重要です。会話のなかで「それはありがたいけれど、こう言ってもらえたほうが嬉しい」と具体的に共有できれば、誤解が生まれる機会は減ります。
善意がすれ違うのは避けられない部分もあります。しかし「違いを認める」姿勢を持ち、定期的に対話の場を持つことで、ハラスメントのリスクを大きく減らすことは可能です。世代間ギャップをきっかけに、むしろ関係性をより健全にする機会と捉えることが、世代間ギャップを解決するにあたっては効果的なのです。
〇第8章:コミュニケーションの再設計──世代を越える対話の技術
世代間ギャップを避けることはできません。しかし、だからといって「仕方がない」とあきらめてしまえば、互いの関係は縮まらないままです。大切なのは、世代を越えて新しい形のコミュニケーションを設計していくこと。そのためには、いくつかの技術的・心理的なアプローチ方法を意識する必要があります。
まず基本となるのが「傾聴」です。相手の話を遮らず、最後まで耳を傾けることは、世代を問わず安心感を生みます。特にZ世代をはじめとした若い世代にとっては、「自分の意見が尊重された」と感じられることが大切であり、昭和世代など年配の世代にとっては「経験を聞き取ってもらえた」という満足感につながります。
次に「問いかけ」です。ただ「どう思う?」と尋ねるのではなく、「この点についてはどう考えますか?」と具体的に聞くことで、相手は答えやすくなります。世代が違うからこそ、持っている視点をさらに具体的に引き出す問いかけは、会話を豊かにする効果があります。
そして忘れてはならないのが「共感」です。共感とは、必ずしも「相手に同意する」ことではありません。「なるほど、そういう考え方もあるのですね」と認めることが、相手に心理的な安心感を与えます。つまり、相手に気持ちを許しても良い、という感覚が生まれるのです。共感を積み重ねることで、世代間の違いが「壁」ではなく「橋」として感じられるようになります。
具体的な場面で考えてみましょう。たとえばZ世代の若手社員がオンライン会議で短いチャットを使って意見を共有したとします。昭和世代の上司は「形式ばらない発言」に戸惑うかもしれません。しかし、ここで「若者は礼儀がなっていない」と切り捨てるのではなく、「チャットはテンポよく意見を出す方法なんだね?」と理解を示すだけで、会話は前向きになります。逆に若手がベテラン社員の長めの説明に出会ったときには、「これは経験からくる金言なんだ」と受け止めれば、双方が歩み寄れるのです。
このように、傾聴・問いかけ・共感という三つの技術を意識するだけで、コミュニケーションの質は大きく変わります。世代間の違いを否定するのではなく、違いを前提に「どうつなぐか」を考えること。それが新しい対話を育てる出発点になります。
〇第9章:制度と文化──組織ができること
世代間ギャップを解消するには、個人の努力だけでなく、組織全体としての制度や文化づくりが欠かせません。とくに現代の職場では、ワークライフバランスを軸にした制度設計が求められています。
たとえばフレックスタイム制やリモートワーク制度は、若い世代が重視する「柔軟な働き方」に応えると同時に、家庭や介護の責任を担うベテラン世代にとっても大きな助けになります。残業を前提としない働き方を浸透させることは、「皆で長時間働くのが当然」という古い常識を和らげ、世代を超えて「効率的に成果を出す」という共通認識を育むことにつながります。
一方で、制度だけでは十分ではありません。そこに文化的な支えがなければ、ルールは形骸化してしまいます。ここで重要な役割を果たすのが社内報やオウンドメディアです。世代を越えた成功事例や、実際の社員の声を紹介することで、「自分たちの会社にもこうした多様な働き方や価値観があるのだ」と実感することができます。記事やコラムを通じて、単なる制度の周知だけではなく「文化としての共有」を広げていくことが重要なのです。
また、世代間の理解を深めるためには、非公式な交流の場も欠かせません。オンラインでの雑談スペースや、世代を越えたワークショップを設けることで、普段の業務では見えにくい相手の人となりが伝わり、距離感が和らぎます。文化とは制度の上に自然と築かれるものですが、その芽を育てる土壌を用意するのは会社や組織の責任でもあります。
結局のところ、制度と文化は車の両輪です。どちらかが欠けても、世代間ギャップを縮める力は半減します。柔軟な制度設計と、それを支える文化的取り組みを両立させることこそが、世代を越えた信頼と協働を実現する組織の鍵になるのです。
〇第10章:世代間ギャップを解消するための研修会──いかに意識を高めるか?
世代間ギャップを縮める取り組みのひとつに、社内研修の活用があります。単なる講義形式ではなく、世代ごとの特徴を理解し、実際に体験を通じて「違いをどう活かすか」を学ぶ場として設計することが大切です。
まず研修の冒頭では、各世代が育った時代背景や価値観を共有するセッションを設けると効果的です。「昭和世代は終身雇用と残業が常識」「Z世代はワークライフバランスを重視」といった特徴を、データや具体的なエピソードを持ち出して紹介すれば、自分たちの常識が相対的なものだと気づくきっかけになります。
次に重要なのは、ロールプレイやグループワークです。たとえば「定時退社をめぐる会話」「オンライン会議での発言スタイル」など、実際に起こりやすいシナリオを演じることで、世代間の認識の違いを体感できます。体験を通じて「なぜ相手がそう反応するのか」が理解しやすくなり、知識だけでは得られない納得感が生まれます。
さらにこうした研修会では、対話の技術を具体的に学ぶことも欠かせません。傾聴、問いかけ、共感といったスキルを短時間の演習で繰り返すことで、実務に応用できる自信がつくのです。「相手の背景を知ろうとする姿勢」が自然に身につけば、日常のコミュニケーションにも前向きな変化が表れます。
最後に忘れてはならないのが「行動計画」の共有です。研修を一過性のイベントにせず、各自が「明日からどんな一歩を踏み出すか」を宣言し合うことで、学びが定着します。「行動計画」の策定は、世代を超えたコミュニケーションを築いていくための道しるべになるわけです。
このように研修会は、世代間ギャップを「問題」として取り上げるだけでなく、「違いを生かす文化」を育てる実践の場になります。組織として定期的に実施することで、世代を越えた信頼と協力の基盤を強めることができます。
〇第11章:将来への展望──ギャップを越えて、関係を編む
世代間ギャップという言葉を耳にすると、多くの人は「どうすれば乗り越えられるのか」と考えます。しかし、本当に必要なのは「乗り越える」ことではなく、「編み直す」ことかもしれません。違いを消し去るのではなく、むしろ違いを素材として、新しい関係を編み込んでいくのです。
コミュニケーションの本質は、相手を自分と同じ考えにすることではなく、相手の「違い」をそのまま受け入れることにあります。若い世代のスピード感や柔軟さ、年配の世代の経験や蓄積を重ね合わせる──どちらも一方的に正しいわけではなく、その双方を組み合わせることで初めて組織を動かす力になっていきます。……異なる色の糸が織り合わさって模様を生み出すように、世代間の差異は、豊かな職場文化をつくる可能性を秘めているのです。
では、私たちはこれから世代間ギャップの解消のために、何をすればよいのでしょうか? まず一人ひとりが「自分の常識は相手にとっての非常識かもしれない」という意識を持つことです。それだけで会話のトーンは変わります。そして、相手の言葉を最後まで聞く、問いかけを工夫する、自分とは違う感覚を一度受け止めてみる──こうした小さな実践が、職場全体の空気を変えていくのです。
世代間ギャップはなくならないでしょう。時代が変われば、また新しいギャップが生まれます。それでも、私たちには「違いを認め合い、関係性を編み直す力」があります。むしろ文化や常識のギャップがあるからこそ、学び合い、支え合う余地が生まれるのです。そして、そこには今までは表に出ていなかった知見が表れてくる、という可能性もあります。
最後に、あなた自身に問いかけたいと思います。
次に世代の違いを感じたとき、「どうして分かってくれない」と壁をつくるのではなく、「この違いをどう編み直せるだろう」と考えてみませんか? その一歩が、世代を越えて関係を育てる出発点になるのです。世代間ギャップの解消方法とは、時代につれ、あるいは皆さんの属している場所や環境によって、ありようや姿形を変えていくものであるのです。
〇おわりに
こちらのコラムでは、世代間ギャップとしての「あるある」や、その心理学的な意味、さらに歴史的な位置づけなどについて見てきました。世代間ギャップは、なにも人見知りをする人など、個人の性格を原因とするものではありません。親と子、上司と部下、年の離れた知人同士や、サービスの現場などで、自然に、そして必然的に表れてくるものです。
要は、世代間ギャップというのは特別な障害であるのではなくて、私たち一般に共通する誰にでも起こりえることなのです。今までは、「昭和世代だから」とか「Z世代だから」と言っていたものも、適切な改善策や研修会などを間にはさめば、より深い相手への理解へと変わっていきます。
世代間ギャップを解消するためには、長い時間を要することもあります。また、時には自分の考え方や感じ方を変えて、相手の立場や経験に合わせてみる、ということも必要になってきます。この古くて新しい問題は、今もつねにアップデートされ続けている事柄なのだと思って良いでしょう。
ここにも書いた事例のように、世代間ギャップの解消のためには、何よりも相手への歩み寄りと理解が必要です。昭和世代にはこんな課題や問題があった、Z世代にはこんな思いや夢がある……そういったことを心のなかに思い描いてみることで、世代間ギャップ(ジェネレーションギャップ)の問題というのは自然に解決されていくものなのです。
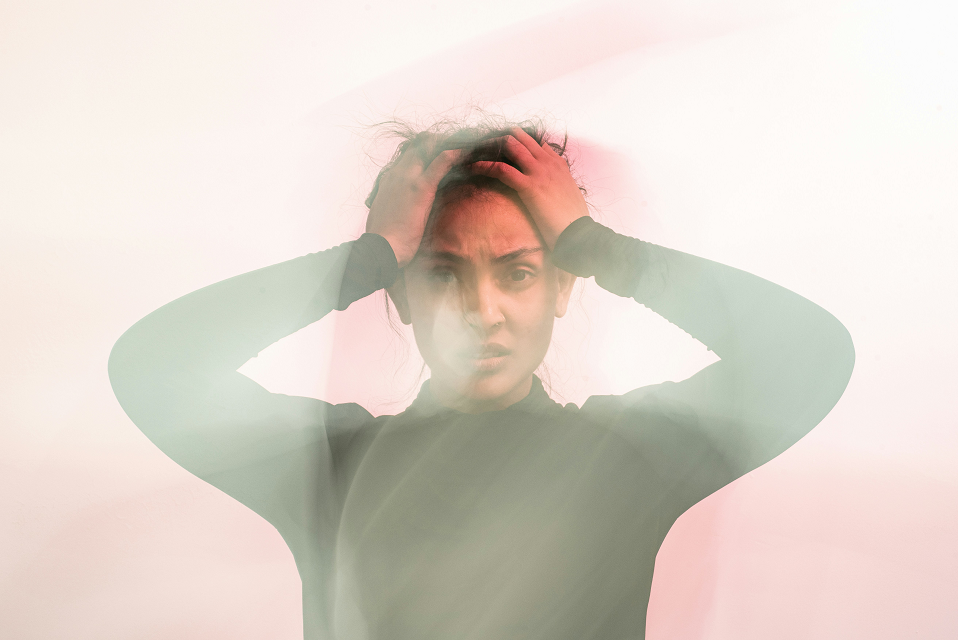
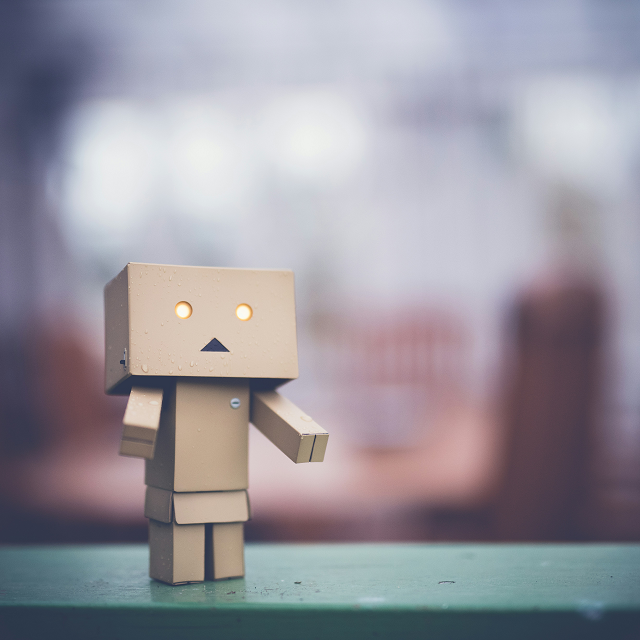
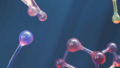
コメント