〇はじめに
ヒューマンエラーという言葉を聞くとき、皆さんはどんな場面や情景を思い浮かべるでしょうか? ──誰かを責める言葉? なじりたい言葉? ……たしかに、この言葉にはそのようなニュアンスも含まれています。あるいは、ヒューマンエラーの12分類についてご存じの方もいるのではないでしょうか。
ヒューマンエラーという言葉そのものの起源ははっきりしませんし、工業化や産業化の進んだ近代になってから使われ始めた言葉であることは間違いないのですが、ヒューマンエラーとはあいまいな響きが保たれている言葉なのです。
「To Err Is Human」……これは、1999年12月に米国のIOM(全米医学アカデミー)がレポートのなかで使用した言葉です。直訳すれば「人は誰でも間違う」という意味になります。このように、「人間が間違える根本的な仕組みについて考えるということは、私たちのリスク管理にとっては欠かせない要素となっています。
いったいこうしたミスが起きる根本原因とは何なのでしょうか? わたしたちはそれを乗り越えるべきなのでしょうか? それとも受け入れるべきなのでしょうか? この記事のなかでは、ヒューマンエラーの根本原因に迫りつつ、いかに私たちがそれを乗り越えていくべきなのか、その対策の方法について示してみたいと思います。
〇第一章 ヒューマンエラーとは何か――定義と誤解
ヒューマンエラーという言葉は、多くの場合「人間のミス」と同じ意味で使われています。
パソコンの操作を間違えたり、計算を一桁まちがえたり、約束の時間を勘ちがいしたり。そうした一見単純な失敗をヒューマンエラーと呼ぶのは直感的でわかりやすいのですが、実際にはこの言葉の意味はずっと広いのです。単なる「不注意」という言葉で片づけるには、人間が環境の中で行う認知や判断のプロセスは複雑すぎます。
人は機械ではありません。注意の配分、判断の速さ、記憶の限界、さらには周囲の状況や職場の雰囲気によって、同じ人が同じ作業をしても結果は変わります。つまり「エラー」とは、個人の力不足や一瞬の油断だけで起こるのではなく、認知・判断・環境が重なり合うなかで生まれる現象なのです。
たとえば、深夜勤務で疲れがたまっている看護師が薬の投与量を間違えてしまうケースがあります。この場合、「注意不足」とだけ言ってしまうのは正しくありません。勤務時間の組み方や交代制の仕組み、確認手順の設定など、背景にある要因も大きく関わっているのです。
ここに、ヒューマンエラーという言葉をどう理解するかの分かれ道があります。
もしそれを、「人が悪い」と短絡的に結びつけてしまうと、意識は教育や罰則といった個人への圧力にかたよりやすくなります。しかしエラーを人間らしさの一部ととらえ、人が環境にどう適応し、どんな制約の中で判断しているのかを理解する視点に立てば、対策は大きく変わります。仕組みの設計を見直すことでエラーを減らす、という方向性が見えてくるのです。
人間らしさとは、もともと状況に合わせて柔軟に動けるところにあります。でもその柔軟さは同時に、判断のゆらぎや思いちがいを生みます。人が直感に頼るからこそ、すばやく対応できる一方で、その直感がずれると誤りが生じてしまうのです。
エラーとは、人間が「機械のように正確ではない」からこそ起きるものですが、それは同時に創造性や適応力の裏返しでもあります。
このように、ヒューマンエラーをただの「ミス」としてとらえるのか、人と環境のかかわり合いとしてとらえるのかで、見える風景は大きく変わります。前者は人を責める物語を生み、後者は仕組みを見直すきっかけになります。ヒューマンエラーをどう定義するかは、その後の改善や対策の方向性を決める大切な出発点なのです。
〇第二章 なぜエラーは起こるのか――ヒューマンエラーの12分類
ヒューマンエラーと一口に言っても、その背景や形態はさまざまです。以下の12分類は、エラーの多様性を理解するための整理のひとつであり、個人の責任を追及するのではなく、原因を構造的に把握する視点を与えてくれます。
1.無知・未経験・不慣れ
知識や技能が不足していると、正しい手順を理解できず誤りが生じやすくなります。新しい作業に慣れるまでの研修やサポートが欠かせません。
2.危険軽視・慣れ
長年の経験や自信が、かえって安全確認の省略につながることがあります。「自分は大丈夫」という思い込みが、油断を招きます。
3.不注意
確認忘れや見落とし、集中力の低下による単純なミスです。作業環境の改善やチェックリストの活用で防止できます。
4.連絡不足
チーム内での情報伝達が不十分だと、認識のズレが積み重なり、結果的にエラーが発生します。報告・連絡・相談(いわゆる「ホウレンソウ」)の徹底が必要です。
5.集団欠陥
職場全体の雰囲気や文化が安全を軽視している場合、個人が注意していてもエラーが起こりやすくなります。組織文化そのものを変えることが重要です。
6.近道・省略行動本能
効率を優先するあまり、重要な手順を飛ばしてしまう行動です。短期的には便利でも、長期的には大きなリスクを生みます。
7.場面行動本能
目の前の作業に集中しすぎて、周囲の状況に気づかなくなる現象です。視野を広く保つ工夫や声かけが役立ちます。
8.パニック
予期せぬ事態に遭遇したとき、冷静な判断ができなくなり、誤った行動を取ってしまうことがあります。訓練やシミュレーションで対応力を高めることが大切です。
9.錯覚
思い込みや見間違いによるエラーです。「こうだろう」という決めつけが正しい判断を妨げるため、複数の確認手段が有効です。
10.中高年の機能低下
加齢に伴う記憶力や判断力の衰えが、ミスを引き起こすことがあります。作業の分担やサポート体制で補う必要があります。
11.疲労など
肉体的・精神的な疲れがたまると、集中力や判断力は確実に落ちます。休憩や勤務時間の適正化がエラー防止に直結します。
12.単調作業による意識低下
同じ作業の繰り返しは注意力を奪い、ミスを誘発します。休憩や作業ローテーションによって集中を維持する工夫が求められます。
この12分類は、独立行政法人労働安全衛生総合研究所の研究員である、高木元也氏が提唱したものです。
ですが、これらの分類は誰かを責めるためのものではありません。むしろ「どんな状況でエラーが起こりやすいか」というヒューマンエラーの原因を知ることで、仕組みや環境をどう変えていくべきかを考える出発点となります。
〇第三章 エラーを防止するために――構造的要因の分析
人間のエラーを考えるとき、私たちはつい「注意不足だったから」「集中していなかったから」といった個人の問題に原因を求めがちです。しかし、認知心理学や人間工学の研究では、エラーが人の弱さだけで生じるのではなく、環境や仕組みとの相互作用の中で起きることを示しています。
まず注目すべきは注意力の限界です。人間の脳は同時に多くの情報を処理できません。電話を受けながら入力作業をすると誤りやすくなるように、注意はすぐに分散してしまいます。これは能力の不足ではなく、人間が本来持っている仕組みそのものです。つまり、注意を前提にした仕組みづくりには限界があるのです。
次に挙げられるのが情報過多です。現代の職場では画面上に大量のデータや選択肢が並びます。その中で重要な情報を見落とすのは自然なことです。航空機の計器や医療現場のモニターでも同様で、必要な情報が整理されていないと、人は正しい判断にたどりつけません。情報の量よりも、どう整理し、どの順番で提示するかが大切になります。
さらに設計ミスも大きな要因です。ボタンの形が似ている、警告音が聞き取りにくい、確認手順が複雑すぎるといった設計は、人間の特性に合わないためにミスを誘発します。ここで重要なのは「人がなぜ間違えたか」を問うことではなく、「なぜ間違いやすい仕組みになっていたのか」を考えて対策を立てることです。
このように、エラーの背景や原因には個人の責任ではなく構造的な要因が潜んでいます。注意や努力に頼るだけでは限界があります。人の特性を理解したうえで、環境や仕組みを見直すことこそが、エラーを減らすための第一歩なのです。
〇第四章 エラーを減らすための思考法――責めずに仕組みを変える
エラーが起きたとき、私たちはつい「誰のせいか」を探してしまいます。けれども、責めることでは本質的な改善にはつながりません。大切なのは「人を責めるより、仕組みを変える」という視点です。人間は完璧ではなく、必ずミスをする存在だからこそ、仕組みの側に工夫を加える必要があるのです。
この考え方を具体的に示す方法の一つが、トヨタ生産方式で有名になった『なぜを5回繰り返す(なぜなぜ分析)』という手法です。たとえば部品の組み立てで不良が出た場合、「なぜ間違えたのか?」で止めるのではなく、「なぜその確認ができなかったのか」「なぜ作業手順がそのようになっていたのか」と掘り下げていきます。原因を個人の注意力に帰するのではなく、仕組みの深い部分に潜む要因を明らかにするのです。
また、医療や航空といった安全性が求められる現場では、チェックリストの導入が広く行われています。人は複雑な状況で手順を完璧に記憶できません。だからこそ、紙やデジタルのリストで「確認する仕組み」をつくり、人間の弱点を補うのです。これも「努力」ではなく「仕組み」でエラーを減らす考え方の実例といえるでしょう。
さらに重要なのは、エラーを学びに変える文化です。失敗の実例や原因を共有できる環境があれば、同じ過ちを繰り返さずにすみます。逆に、責める文化ではミスが隠され、改善の機会が失われてしまいます。
「人を責めるより仕組みを変える」という原則は、組織に安心感をもたらし、同時に生産性や安全性を高めます。人の限界を前提に、仕組みを工夫することこそが、エラーを減らすための本質的な思考法なのです。
〇第五章 テクノロジーとヒューマンエラー――AIは万能か?
近年、AIや自動化技術はさまざまな分野で導入され、ヒューマンエラーを減らす有効な手段と見なされています。たとえば、車の自動ブレーキや医療分野での診断支援システムは、人間が見落としやすい状況を補い、大きな成果を上げています。人間の弱点を補完する存在として、テクノロジーは確かに頼もしいものです。
しかし、「AIがあればすべて解決する」と考えるのは危険です。AIにはバイアス(「偏見」や「思い込み」)の問題があります。学習に使われるデータが偏っていれば、そのまま判断も偏ってしまいます。過去の事例に基づいて判断するAIは、未知の状況や例外的なケースに弱いのです。
また、人間の判断を完全にAIに置き換えることもできません。たとえば、医師が患者の表情や声の調子から微妙な変化を感じ取るような「文脈や過程に基づく判断」は、数値やデータだけでは表しきれません。AIは補助的なツールとしては有効ですが、人間の直感や経験をすべて代替できるわけではないのです。
さらに、テクノロジーの過信にも注意が必要です。自動化されたシステムに頼りきると、人間のほうが「見ているつもり」で確認を怠り、逆に大きな事故につながることがあります。自動操縦の飛行機でも、最後の判断はパイロットが下さなければならないのと同じです。
つまり、AIや自動化は「万能の解決策」ではなく、人間の弱点を補いながら共存する道具なのです。テクノロジーにできることとできないことを見極め、人間の判断と組み合わせることで、はじめてエラーを減らすための対策を構築できます。大切なのは「任せきりにしないこと」。人とAIが互いの特性を理解し、補い合うことこそが、未来に向けての現実的な道筋なのです。
〇第六章 現場から学ぶ――医療・航空・製造業の事例
ヒューマンエラーを減らすための工夫は、すでに多くの現場で実践されています。その事例を見ていくと、「人を責めるより仕組みを変える」という考え方がどのように形になっているのかがよくわかります。
まず医療現場では、チェックリストが広く使われています。手術前に患者の名前や部位を確認する「タイムアウト」や、薬剤投与の際の二重チェックなどは、忙しい環境での思いちがいを防ぐ大切な仕組みです。人が記憶だけに頼るのではなく、リストを使って確認することで、安心感と安全性を高めています。
航空業界では、CRM(クルー・リソース・マネジメント)という考え方が導入されています。これは「一人の判断に依存しない」ための仕組みです。たとえば副操縦士が機長の判断に疑問を感じた場合には、遠慮なく意見を述べるように訓練されています。立場の上下ではなく、チーム全体で安全を守る文化をつくることで、致命的な事故を防いでいるのです。
製造業では、ポカヨケ(「ミス防止装置」)が有名です。たとえば部品の向きが間違っていると装置が作動しない仕組みや、ネジが一本でも不足していれば次の工程に進めない仕組みなどが挙げられます。作業者にただ「気をつけて」と言うのではなく、間違えられない設計にすることがポイントです。
これらの事例に共通しているのは、「人間は必ずミスをする」という前提に立っていることです。そして、その弱点を補う仕組みを環境に組み込むことで、結果的に人も組織も守られるのです。現場の工夫には、ヒューマンエラーを減らすためのヒントがたくさん詰まっています。
〇第七章 ヒューマンエラーの具体例──より詳しい考察
ヒューマンエラーは抽象的に語られるだけでは実感しにくいものです。ここでは、実際の現場を想定した3つの例を紹介し、それぞれにどのような対策が考えられるのかを示してみましょう。
事例1:医療現場での投薬ミス
深夜の病棟で、看護師が疲労のなか似た名前の薬剤を取り違えて投与しそうになった。薬剤棚には複数の類似名称の薬が並び、ラベルも小さな文字で判読しづらかった。幸いダブルチェックの途中で発見されたが、患者の命にかかわる重大なリスクを孕んでいた。
→ 対策:薬剤ラベルの文字を読みやすい大きさにし色分けもする。必ず二人で確認する「ダブルチェック」を徹底する。
事例2:工場ラインでの部品装着ミス
製造ラインで作業員が、形がほぼ同じ二種類の部品を誤って装着してしまった。完成品の検査で発見されたが、出荷直前まで気づかれず、工程全体が停止する事態に発展した。原因は部品の形状が似すぎており、作業現場の照明も十分でなかったことにあった。
→ 対策:部品ごとの色分けや形状を工夫し、作業場所も見通しを良くし明るくする。さらにセンサーによる自動判定を導入。
事例3:オフィスでのメール誤送信
営業担当者が取引先へ資料を送る際、似た名前の会社のクライアント宛に誤って送信してしまった。ファイルには機密情報が含まれており、発覚後に大きな対応コストが発生した。背景には、忙しい業務の中で自動補完機能に頼りきったチェック不足があった。
→ 対策:送信前に宛先を確認する警告ポップアップの導入、重要メールでは上司承認を必須とする仕組みを徹底。また、職場環境をつねに集中できるものへと整備する。
これらの事例が示すのは「人は必ず間違える」という現実です。しかし、工夫を加えればエラーは未然に防げます。大切なのは責任を追及することではなく、仕組みや環境を見直し、人間の特性に寄り添った対策を重ねていくことなのです。
〇第八章 改善へのステップ──ヒューマンエラー対策の具体例
ヒューマンエラーを減らすためには、「どんな対策が実際に有効に働いたのか」を知ることが大切です。ここでは、さまざまな現場で起こりうるエラーに対して、どのように仕組みを工夫したのかを具体的に見ていきましょう。
事例1:小売店舗でのレジ金額入力ミス(過去の事例)
──混雑時、店員が商品の単価を誤入力し、顧客への過剰請求が発生。レジ画面は小さく、確認する余裕もなかった。
→ 対策:スキャナーを利用し、バーコード入力を原則化。画面には商品名と画像を大きく表示し、店員と顧客の双方が即座に確認できるように変更した。その結果、入力ミスは激減し、顧客からのクレームも大幅に減少した。その反面、バーコード未登録商品(割引商品など)への対応に手間がかかるという問題が浮上し、登録作業の効率化が次の課題となった(現在では、割引の値札そのものにもバーコードを追加するということで、対応している)。
事例2:建設現場での安全帯未装着
──高所作業中、作業員が安全帯を着け忘れ、危うく墜落しかけた。現場は時間に追われており、装着確認が「自己責任」に任されていたことが背景にあった。
→ 対策:作業開始時にチーム全員で安全帯を確認する「相互チェック」を導入。さらに、足場の入口にセンサー式ゲートを設け、安全帯が装着されていないと通過できない仕組みにした。その結果、装着忘れはほぼゼロになり、現場の安全意識も高まった。また、朝礼の場で従業員相互のコミュニケーションを推進するなど、職場意識の向上に勤めた。一方で、ゲートの導入コストや設置場所の制約といった課題も明らかになり、今後の改善テーマとして残された。
事例3:研究所でのサンプル取り違え
──実験用サンプルを冷凍庫から取り出す際、似たラベルの容器を間違えて使用してしまった。数週間の研究データが無駄になった。背景には、手書きラベルの判読性の低さと、管理システムの更新不足があった。
→ 対策:バーコードによる一元管理を導入。取り出し時にスキャナーで確認し、間違ったサンプルならアラートが鳴る仕組みにした。ラベルも耐久性の高い印刷方式に統一。これにより取り違えはほぼ解消され、研究データの信頼性が向上した。ただし、システム導入後はバーコード機器の保守や故障対応が新たな課題となり、継続的な運用改善が不可欠であることがわかった。また、それと並行して新人研究員への研修を徹底して行うようにし、専門用語や手順についての現場での共有、意識改革を行った。
これらの例に共通するのは、「注意力に頼らず、仕組みを変える」点です。人間の限界を前提にした改善策を組み込むことで、ヒューマンエラーや、その原因となる事柄は大幅に減らせます。同時に、対策の実施によって新しい課題も見えてきます。その課題をさらに改善へとつなげることが、持続的にエラーを減らすうえでの重要なステップとなるのです。
〇第九章 エラーを受け入れる文化――「失敗知(失敗知識)」への転換
エラーに直面したとき、多くの人は恥ずかしさや後ろめたさを感じます。「間違えたら評価が下がる」「信用を失う」と考える文化では、ミスは隠されがちです。しかし、それでは改善のチャンスは失われてしまいます。エラーを「恥」ではなく「学び」として受け止める文化への転換が、今求められています。
近年では、あえて失敗を共有する取り組みも広がっています。たとえば「失敗自慢カンファレンス(FailCon)」と呼ばれるイベントでは、研究者や実務者が自分の失敗をオープンに語ります。そこで笑いや共感が生まれ、参加者同士が安心して学び合える場となります。失敗を隠さず共有することで、個人だけでなく組織全体が成長できるのです。これは、あなたの会社でも気軽に導入できる例と言えるでしょう。
教育の現場でも、リフレクション(振り返り)の実践が注目されています。生徒や学生が「どこでつまずいたか」を振り返り、それを次に活かす習慣を身につけることは、失敗を学びに変える文化を育む第一歩です。「間違えたら終わり」ではなく「間違えから次へ」という視点を持つことが、人を大きく成長させます。
また、哲学的に見れば、失敗は人間の限界を映し出す鏡でもあります。私たちは完全ではなく、間違いを通して自分の弱さや偏りに気づきます。そしてその気づきこそが、次の行動をよりよいものにしていくのです。エラーは単なる欠点ではなく、未来を形づくるための素材なのだと考えることで、エラーそのものをポジティブにとらえることができます。
「失敗知(失敗知識)」とは、失敗を知恵に変える力です。その文化を組織や社会に根づかせることができれば、ヒューマンエラーは恐れるべきものではなく、進歩や改善への原動力へと姿を変えるでしょう。
〇第十章 未来への提案――人間と仕組みの共進化
これまで見てきたように、ヒューマンエラーは人間の弱さだけでなく、環境や仕組みとの相互作用の中で生まれてきます。そのため、エラーを「完全に排除する」ことは現実的ではありません。むしろ大切なのは、人と仕組みが共に進化し続ける社会をつくることです。
会社の未来に向けて必要なのは、柔軟性を持った仕組みです。どれほど精密に設計された制度やシステムでも、現実の状況は常に変化します。だからこそ、仕組みには改良の余地を残し、人間が新しい課題に気づいたときに修正できるようにしておくことが重要です。完成された「動かせない仕組み」ではなく、その場での対策や、改善を前提とした「生きた仕組み」が求められます。
また、人と仕組みのあいだに対話があることも欠かせません。現場の声が設計に反映されること、利用者が感じる不便や危険がきちんと共有されることによって、仕組みは人間の特性に寄り添ったものになります。トップダウンの命令ではなく、双方向のやり取りを重ねることで、ヒューマンエラーや、その原因自体を減らす道が開けていきます。
さらに、社会全体が失敗を受け入れ、再設計していく力を持つことが必要です。一度の失敗で全体を否定するのではなく、そこから学び、より良い仕組みに作り替える。エラーを「進化のきっかけ」として扱える文化こそが、未来を支える基盤となります。そのためにも、ヒューマンエラーが起きる際の12分類については、しっかりと把握しておくことが大切です。
エラーは人間の限界を示すと同時に、新しい可能性をひらく扉でもあります。人と仕組みが共に成長していく未来を描けるなら、エラーは恐れるものではなく、希望をつなぐ存在に変わりうるのです。私たちが目指すべきは、完璧さではなく、共進化によってより豊かな社会をともに育てていくことだと言えます。
〇おわりに
いかがだったでしょうか?
ヒューマンエラーは近代になってから「発見」されたものですが、現代の社会では、それを乗り越えるための様々な試みが展開されていることが分かります。高木元也氏による12分類などもそうですし、「ポカヨケ」という考え方の浸透や、「失敗自慢カンファレンス(FailCon)」の開催などは、その主だった例だと考えて良いでしょう。
ヒューマンエラーを人が追及するとき、その根底には、「To Err Is Human(人は誰でも間違う)」という考えが存在していなければいけません。そうでなかった場合、人はひたすら犯人を追及することにつとめ、それを努力義務を行ったとして糾弾してしまうでしょう。ですが、そうした行為によって「ミス」の根本原因はなくならないのです。
ヒューマンエラーをいかに防ぐかということは、「いかに人間を理解するか」ということにもつながってきます。場合によってはシステムやルールを変えることによって、それに対処することもできるでしょう。ですが、根本のところでは、わたしたちは「To Err Is Human」をまず認めなければいけないのだと言えます。
企業や家庭生活の場面でも、「失敗が許されない場面」が増えていく今日、ヒューマンエラーがなぜ起こるのかをつきつめていくということは、「ミスのない社会」「不幸の少ない社会」を構築することにも、つながってきます。みなさんもぜひこの機会に、ヒューマンエラーとは何なのかを考え、「ミスをする人間を愛する」という立場に立っていただければと考えています。
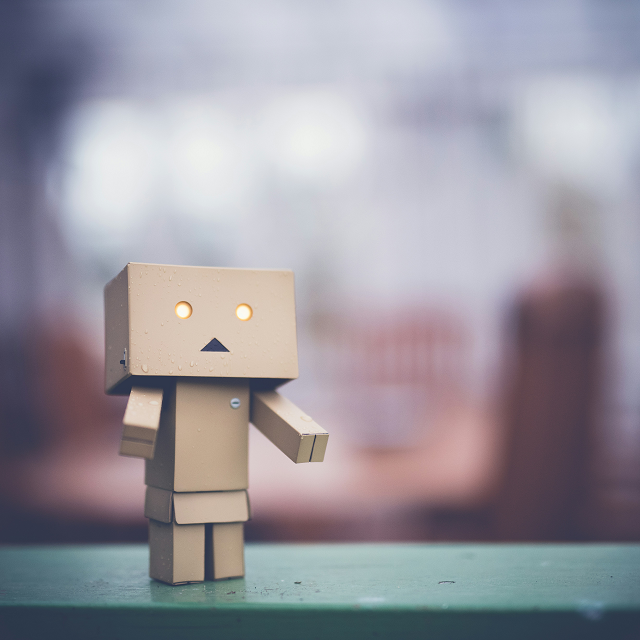
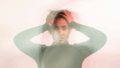
コメント